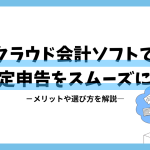COLUMN経営コラム

COLUMN経営コラム

クラウド会計ソフトを使用すれば税理士への顧問料は抑えられる?
投稿日:2024.07.18
更新日:2024.07.25
税務経理クラウド
クラウド会計ソフトの登場により、決算・申告業務の効率化が進み、中小規模の個人事業主であれば自身で決算・申告業務を対応している方も少なくありません。また、現在税理士に記帳や税務申告を依頼している方々の中には、「自社でクラウド会計を使って記帳すれば、顧問料を抑えられるのでは?」と思われている方もいらっしゃるかもしれません。
本記事では、「クラウド会計ソフトを導入すれば、税理士は不要になるのか?」、「顧問料は下がるのか?」、「クラウド会計に詳しい税理士をどのように見つけ、どのように選べば良いのか?」といった、クラウド会計と税理士に関する疑問について解説します。クラウド会計を導入されている方や、税理士と顧問契約について検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
▼ この記事の内容
クラウド会計利用時の税理士の要否について
ここでは、クラウド会計利用時の税理士の要否について解説します。クラウド会計は自社の会計業務の効率化をもたらしますが、正しい決算書・申告書を自動で作成するわけではありません。クラウド会計を利用した場合、AIが推測した「間違った処理」が永遠に登録される可能性があります。また、「残高がマイナス」などの致命的なエラーが頻発することもあります。
さらに、自動連係により売上が二重計上されるリスクや、決算処理が正しく行われず経費を過大計上してしまう税務調査のリスクも存在します。以下では、税理士が必要な場合と税理士が不要な場合について説明します。自社の状況に照らし合わせて税理士への依頼を検討しましょう。
税理士が必要な場合
売上が多く取引が複雑な個人事業主の場合、税理士に依頼することで様々なメリットが得られます。売上高が一定規模を超えると、税務調査の対象となる可能性も高くなるため、より正確な記帳と税務的に正しい確定申告が必要になります。事業規模が大きくなると、個人事業主であっても記帳や確定申告の難易度が上がるだけではなく、法人成りの検討や優遇税制の活用、専従者給与の活用などなど、専門的な知識が必要な節税策の効果が大きく出る可能性があります。
税理士に依頼することで一定の顧問料を負担する必要はありますが、これらの会計上の課題に対して有効なサポートやアドバイスが得られるでしょう。
また、法人の経営者であれば顧問税理士を付けるのはほぼ必須です。これは、多くのクラウド会計ソフトでは法人の申告機能が未実装であり、対応ができていない状態にあるためです。また、法人の決算や申告は複雑であるため、これらすべてを自社で対応するには相当の能力と知識が必要となる点も、顧問税理士への依頼が必要となる要因の一つです。
税理士が不要な場合
売上が少ない個人事業主の場合、税理士に頼むメリットが少なく、支払う顧問料に見合うだけの効果が見込みにくいです。取引の仕組が単純な方が多く会計や確定申告の難易度が低いため、システムベンダーのサポートをうまく活用すれば、自身でできるようになるケースもあります。ただし、今は売上高が少ないけれども、組織化や法人成りを検討していたり、拡大志向で売上の増加が予測されていたりする場合は例外です。
クラウド会計によって税理士の顧問料は安くなるのか
ここでは、クラウド会計の導入によって税理士の顧問料を押さえられるのか否かについて解説します。税理士の顧問料は「記帳代行料」と「監査・決算料」とに大別され、それぞれ業務の内容が異なります。依頼している業務の一部を自社で対応することにより、顧問料を抑えることができる可能性があります。以下で詳しく説明していきます。
顧問料には「記帳代行料」と「監査・決算料」とに分かれる
顧問料には「記帳代行料」と「監査・決算料」の2つがあります。記帳代行料とは、請求書や領収書を会計事務所に共有し、会計ソフトへの入力を依頼する場合の費用です。一方、監査・決算料とは、会計ソフトに入力されたデータのチェックや、税務上の判断、決算・申告を行う費用です。顧問料を安くしたいと考える場合、「どちらを安くしたいのか?」という視点を持つと良いでしょう。
クラウド会計の導入で顧問料を安く抑える方法
クラウド会計への入力を自社で行うことで、記帳代行料を減らすことが可能です。また、クラウド会計を専門とし、低価格で請け負う会計事務所に依頼することも一つの方法です。
顧問料を安く抑えたい場合の注意点
顧問料を安く抑えたい場合、自社で対応する業務と顧問税理士へ依頼する業務の範囲を、事前に確認しておくことが重要です。対応を依頼する業務の範囲を明確にすることで、後々のトラブルを防ぐことができるでしょう。また、決算直前の変更は、手続きが煩雑となるだけでなく会計上のミスに繋がる恐れもあることから避けるべきでしょう。
顧問料をケチってはいけないのはこんな人たち!
ここでは、顧問料をケチってはいけない事業者について、個人事業主と法人のそれぞれに分けて解説します。売上高の拡大や中長期的な成長を見据えて施策を検討している場合、顧問料を抑えることに注力するのではなく、専門家のサポート・アドバイスを積極的な活用するとよいでしょう。以下で詳しく説明していきます。
法人化を目指している個人事業主
法人化を目指している個人事業主の場合、顧問料をケチるべきではありません。なぜなら、法人化を検討する際には将来を見据えた綿密なシミュレーションが必要であり、検討すべき論点も多数あるからです。法人運営の経験が無い中でこれらを自身で対応するのは非常に困難であり、豊富な経験と実績を持つ税理士に相談し、専門家の目線でのサポートを受けることが最適であると言えるでしょう。
売上高1億円以上である・もしくは目指している法人
売上高1億円以上である・もしくは目指している法人の場合、「経営管理」や「財務」の視点を持って会計業務を進めることが重要になってきます。そのため、顧問料を抑えることだけを考えるのではなく、中長期的な成長を見据え、「経営管理」や「財務」の視点から会社を成長させるための提案をくれる税理士を選ぶと良いでしょう。
クラウド会計に強い税理士の選び方・探し方
ここでは、クラウド会計に強い税理士の選び方・探し方について解説します。クラウド会計を真の意味で活用できる税理士はまだまだ少ないと言われています。しかし、その数は確実に増えてきており、クラウド会計に理解がある税理士を見つけることは決して不可能ではありません。そのためには、以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。
クラウド会計を活用できる税理士はまだまだ少ない
クラウド会計は比較的歴史が浅く、全ての税理士がその利用方法やメリットを理解しているわけではありません。日本税理士会連合会の資料によれば、全国の税理士登録者数は令和6年6月末日現在で81,028人です。
一方、クラウド会計ソフトfreeeの認定アドバイザーとして登録されている数は約2,000件、マネーフォワードの公認メンバーとして登録されている数は約2,900件と、全体の数に対してはまだまだ割合が低いです。そのため、税理士を選ぶ際には、クラウド会計に対する理解があるかどうかを確認することが重要です。
(出所: 日本税理士連合会https://www.nichizeiren.or.jp/cpta/about/enrollment/)
(出所:freee認定アドバイザー検索画面 https://advisors-freee.jp/advisors/search)
(出所:マネーフォワード 公認メンバー検索画面 https://biz.moneyforward.com/mfc-partner/search/zeirishi/?)
クラウド会計各社の「税理士検索サイト」を活用
クラウド会計サービスを提供している企業の中には、自社のサービスを活用している税理士を検索できるサイトを提供しているところもあります。これらのサイトを活用することで、クラウド会計に強い税理士を見つけることができます。
実際に会って話を聞いてみる
税理士を選ぶ際には、実際に会って話を聞いてみることも大切です。クラウド会計に対する理解だけでなく、自社のビジネスに対する理解や、税務に関する専門的な知識など、税理士としての総合的な能力を確認することができます。
まとめ
本記事では、クラウド会計利用時の税理士の要否や顧問料は安くなるのか否かについて解説しました。クラウド会計を導入したからといって、「税理士が不要になる」「税理士への顧問料が減る」わけではなく、顧問料は税理士に求めるサービス内容によって異なります。クラウド会計も税理士も、それぞれの目的に応じて効果的に活用することが重要であると言えるでしょう。
FLAGSグループでは、マネーフォワードプラチナ公認メンバーとして、400件以上のクラウド会計導入支援の経験を持つ10名以上の専門家チームが、経理業務全般のサポートを提供します。クラウド会計の導入を検討している方は、問い合わせフォームや電話にてお気軽にご連絡ください。