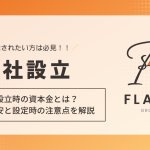COLUMN経営コラム

COLUMN経営コラム

会社設立を自分でする前に知るべきこと|税理士が解説する基礎知識
投稿日:2025.05.28
更新日:2025.06.29
経営
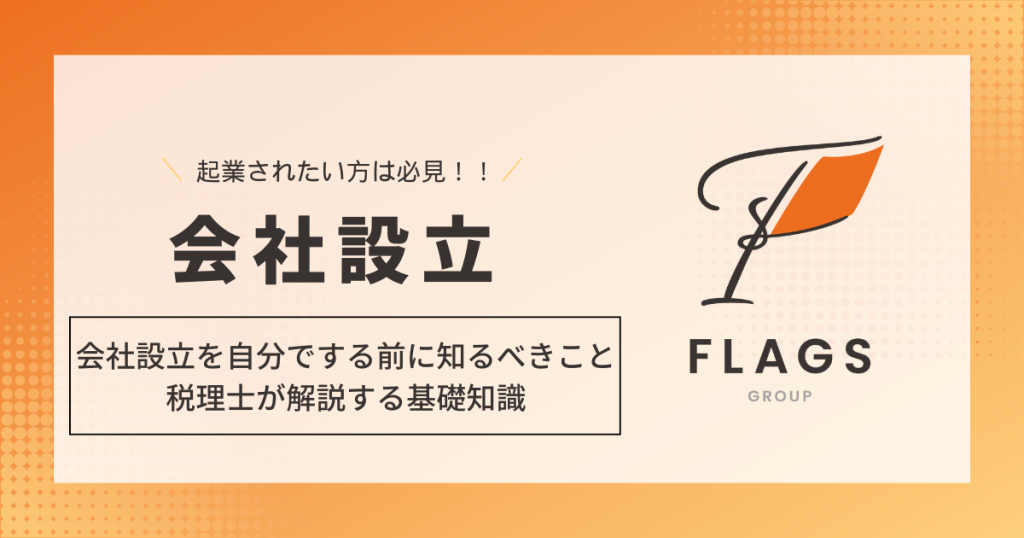
会社設立を自分で行うことは、費用を抑える手段として非常に魅力的です。しかし、必要な手続きや書類の準備、注意すべき点がいくつかあります。この記事では、会社設立の方法について順を追って解説し、途中で生じる可能性のある疑問を解決できるように説明します。特に、自分で進める際のメリットとデメリットをしっかり把握して、スムーズな会社設立を目指しましょう。
▼ この記事の内容
専門家に依頼する場合との違い
会社設立を自分で行う場合と、専門家に依頼する場合では、それぞれにメリットとデメリットがあります。メリット・デメリットを正しく理解した上で自身にとって最適な方法を選びましょう。以下で詳しく説明していきます。
自分で行う場合と専門家に依頼する場合の比較
会社設立を自分で進める場合、費用(外注費用など)が最低限で済む・会社設立の経験を積みながら学べることがある・身に付いた会計法や税金の知識を今後に活かせるなどのメリットがあります。
その反面、手続きに多くの時間と労力を要する点が課題となります。定款などの書類作成作業や手続きに時間が取られ、事業準備の時間が圧迫される恐れもあります。経験の少ない業務で調べ物が多くなるのもデメリットでしょう。
会社設立に関わる手続きは多岐にわたるため、「何から調べればいいのかもわからない」と、途方に暮れてしまうケースも少なくありません。ミスが起こることがある点も困るところです。定款作成に失敗すると、3万円の手数料がかかります。
一方で、専門家に依頼すると、手続きが円滑に進むことで時間を短縮でき、本業に集中できるためミスを防ぐことができるという利点があります。専門家に会社設立の代行を依頼した場合、会社設立本人がやるべきことは「法人用の実印を作る」「出資金(資本金)を払い込む」のみです。専門家には起業に当たっての不安や節税対策などの相談もできます。
ただ、その分の費用が発生します。外注費ですね。また、専門家を探す手間がかかります。顧問契約しないと依頼できない場合もあります。
どちらの方法を選択するかは、個々の状況やニーズに応じて慎重に判断することが大切です。詳しい内容については、以下の記事をご参照ください。
参照:会社設立にかかる費用は?必須費用から節約方法まで徹底解説
会社設立の流れと手続き方法は?
自分で会社を設立する方法を考える前に、一般的な会社設立の流れと手続き方法を知っておく必要があるので、解説しましょう。
会社設立の手順
まずは会社設立の手順を見てみましょう。
会社の概要を決める
会社を設立するに当たって、概要(基本事項)をまず決めましょう。次のようなことです。
- 社名(商号)
- 所在地
- 資本金
- 設立日
- 会計年度
- 事業目的
- 株主の構成
- 役員の構成
社名(商号)
社名(商号)はいわば会社の顔です。会社のイメージ・雰囲気・事業内容が伝わるような社名を付けることが大事です。個人事業主が会社を設立する場合は、使っていた屋号を引き継ぐこともできます。
なお、社名を付けるときは、他の会社や団体と紛らわしいものは避けましょう。類似の社名を使ってしまうと、後で法的なトラブルになることもあるからです。
所在地
所在地とは会社の住所のことです。法律上の住所に当たりますが、事業活動を行う場所と異なっていても問題はありません。自宅、レンタルオフィス、バーチャルオフィスなどを所在地にしても差し支えありません。
資本金
資本金は最低1円でも構わないのですが、あまり額が低いと、金融機関からの信用が得られず、融資を受けにくくなります。
設立日
会社の設立日は法務局に設立の登記申請をした日になることをご留意ください。設立日は自由に決められますが、状況によっては指定どおりにならないこともあります。
会計年度
会社は一定期間ごとに決算書を作成しないといけないのですが、この区切りになる年度が会計年度です。
事業目的
会社がどのような事業を行うのか、事業目的を定める必要があります。事業目的は、取引先や金融機関もチェックする大事な項目です。
株主の構成
株主とは、株式会社の株式を持っている人のことです。
役員の構成
会社の運営を担当するのが役員で、取締役や代表取締役、監査役などから構成されます。会社設立時には最低限一人の取締役の選出が必要です。自分を取締役にしても構いません。
法人用の実印を作成する
法務局において書面で設立登記申請をする場合は、実印が必要なので作成しておきましょう。会社の社名が決まった時点で実印を作成し、印鑑届出書も提出します。
なお、法改正があり、2021年2月15日から設立登記をオンラインで行う場合は、実印の届出をしなくても良くなりました。ということは、実印を作成しなくても構わないということになりますが、書面による申請時だけでなく、会社設立後も実印が必要な場面が多々生じます。
そのため、最初に実印を作成しておかないと、後で作成することになり面倒です。二度手間になってしまうケースもありますから、会社設立時に実印を作成しておくのがおすすめです。
法人口座の開設には銀行印、請求書や納品書には角印(社判)を押印するので、合わせて作っておくと良いでしょう・
定款を作成、認証を受ける
会社を設立する際は定款を作成しないといけません。定款とは会社を運営していく上でのルールを記載した大切な書類です。定款には必ず記載することになっている「絶対的記載事項」というものがあり、これは法律で内容が定められています。
定款に必ず記載すべき項目を挙げてみましょう。
- 称号(会社の名称)
- 事業目的(記載すべき数に制限はないが、5~10個、多くても15個くらいが目安)
- 本店所在地
- 資本金(会社運営の元手となる資金)
- 発起人の氏名及び住所
次は状況に応じて定款に記載する項目を挙げてみましょう。
- 株券や株主に関する事項
- 役員報酬に関する事項
- 配当金に関する事項
定款に必ず記載すべき事項(絶対的記載事項)が含まれていないものは、無効になってしまいますから、お気をつけください。
参照:会社設立の定款とは?記載内容や電子定款の違いを徹底解説
発起人の口座に出資金(資本金)を払い込む
定款を作成したら、その日以降に発起人の口座に出資金(資本金)を払い込みましょう。この時点では、会社設立登記が済んでいないため、会社用の銀行口座を作成できませんから、発起人の個人口座に出資金を払い込むのです。
登記申請書類を作成し、法務局で申請する
続いて登記申請書類を作成しなければいけないので、次のような必要書類を準備しましょう。
- 資本金の入金証明
- 印鑑証明書
- 発起人の決定書
- 株式会社設立登記申請書(社名や本店所在地、登録免許税の金額、添付書類などの一覧を記載する)など
必要書類の準備ができたら法務局に提出するのですが、これらの手続きを紙で行うと、書類の準備から郵送に至るまで手間がかかります。そこで急ぎの場合は、インターネット上で手続きが可能なオンライン申請がおすすめです。
法人登記を行った日が会社の設立日ということになります。
設立登記後の手続きとは?
会社設立登記が完了した後の手続きも見てみましょう。
会社設立後は、税金や社会保険、労働保険の手続きが必要
会社設立後は、税金や社会保険、労働保険の手続きが必要になるので、それぞれの手続き内容を確認してみましょう。
税金関係の手続き
税金関係では、まず法人税に関する届出をします。必ず提出するものは次のようなものです。
| 提出する書類 | 内容 | 提出期限 |
| 法人設立届出書 | 法人税や消費税などの国税を納付することになる法人を新しく設立したことを示す書類 | 法人設立日以降2ヶ月以内 |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 原材料や商品在庫など、仕入れた商品の材料・資材などの棚卸資産の計算方法を示した書類 | 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 建物や設備など時間とともに価値が下がる資産をどのように経費に算入するかを示した書類 | 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで |
上記の届出書の提出先は会社の本店所在地が位置している地域の管轄税務署です。
次は必要に応じて提出するものです。この場合、提出先によって準備する書類が異なります。
▶提出先が給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
| 提出する書類 | 内容 | 提出期限 |
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 役員や従業員に報酬、給与を支給するときに提出する書類 | 給与支払事務所等を設けてから1ヶ月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 源泉所得税の納期の特例を受けるために必要な書類 | 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合) |
▶提出先が納税地の所轄税務署
| 提出する書類 | 内容 | 提出期限 |
| 青色申告の承認申請書 | 青色申告で申告したいときに提出する書類 | 法人設立日以降3ヶ月間を経過した日または最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで |
| 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 資本金の額または出資金の金額が1,000万円以上の時に提出する書類 | 速やかに |
| 適格請求書発行事業者の登録申請書 | 設立時から適格請求書発行事業者の登録を受けたいときに提出する書類 | 最初の事業年度の終了の日まで |
続いて、法人住民税・法人事業税の届出に関する手続きを確認してみましょう。
この場合は、本店所在地となる都道府県税事務所と市町村役場へ法人設立届出書を提出します。ただし、東京23区内に本店所在地がある会社の場合は、市町村役場への提出は免除され、都税事務所への提出だけで済みます。
全体の流れを再チェックしましょう。設立登記が済む⇒重要必要書類を管轄税務署に提出する⇒都道府県税事務所・市町村役場へ同書類の届出をする。このような流れになります。
社会保険関係の手続き
会社設立後の社会保険関係の手続きでは、まず健康保険・厚生年金保険加入に関する届出を行います。加入手続きは年金事務所で行い、次のような書類が必要になります。
| 必要書類 | 内容 |
| 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 事業所が新たに健康保険・厚生年金保険を利用し始めるときにこの書類が必要 |
| 健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書・同意書 | 強制適用事業所となっていない事業者が健康保険・厚生年金保険を利用したときにはこの書類が必要 |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 採用した従業員に新たに健康保険・厚生年金保険に加入させるときはこの書類が必要 |
| 健康保険 被扶養者(異動)届 | 家族を被扶養者にしたいときはこの書類が必要 |
| 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書 | 健康保険・厚生年金保険料を口座振替で納めたいときはこの書類が必要よって納付するときに必要な書類 |
上記の届出をする際は、注意点が1つあります。書類提出日から遡って90日以内に発行された法人登記簿謄本(商業登記簿謄本)の原本も必要ですから、ご注意ください。
労働保険関係の手続き
従業員を雇うときは、労災保険と雇用保険への加入手続きをしないといけません。手続きを行う場所は、労災保険の方が労働基準監督署で、雇用保険はハローワークです。それぞれの保険で必要になる書類と提出期限を確認してみましょう。
▶労災保険に必要な書類
| 必要書類 | 提出先 | 提出期限 |
| 労働保険保険関係成立届 | 所轄の労働基準監督署 | 保険関係が成立した日の次の日から10日以内 |
| 労働保険概算保険料申告書 | 所轄の労働基準監督署 | 保険関係が成立した日の次の日から50日以内 |
| 履歴事項全部証明書(写)1通 | 所轄の労働基準監督署 | 保険関係が成立した日の次の日から10日以内 |
▶雇用保険に必要な書類
| 必要書類 | 提出先 | 提出期限 |
| 雇用保険適用事業所設置届 | 所轄のハローワーク | 設置の日の翌日から起算して10日以内 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 所轄のハローワーク | 資格取得した日の翌月10日まで |
| 労働保険保険関係設立届(控) | 所轄の労働基準監督署あるいはハローワーク | 保険関係が成立した日の次の日から10日以内 |
| 労働保険概算保険料申告書(控) | 所轄のハローワーク | 保険関係が成立した日の翌日から50日以内 |
設立登記後の手続きについて付記しておくと、法律上の許認可手続きが必要な事業の場合、行政書士に依頼しなければいけないケースが出てきます。
自分で会社を設立する方法とは?
ここでは、会社設立の手続きを自分で行うに際して、会社設立の基本的な流れや手続きの順序などについて解説します。まずは、全体像を把握するために、どのような書類や手続きが必要となるのかをしっかりと理解しましょう。以下で詳しく説明していきます。
会社設立の基本的な流れ
会社設立を行う際には、最初のステップとして「定款」の作成が必要です。この定款は、会社の基本的な運営ルールを定めた重要な書類であり、設立手続きの土台となります。
定款には、会社名や事業目的、具体的な事業内容、資本金の額、そして設立時における取締役や代表者に関する情報を詳細に記載します。さらに、公証人役場で認証を受けることが法律で義務付けられています。
定款の認証が完了した後は、「登記申請」を行う手続きに移ります。この登記申請を行うことで、会社が法人として法的に成立することになります。申請には、認証済みの定款、資本金の払込を証明する書類、役員が就任を承諾したことを示す書類などが必要です。申請手続きが完了すると、法人番号が付与され、会社の設立が正式に承認される運びとなります。
どのような順序で進めれば良いか
会社設立の手順は、以下の順序で進めるとスムーズです。まず、定款を作成し、公証人役場で認証を受け、その後、資本金を銀行に払い込む必要があります。次に、登記申請を行い、登記簿謄本を取得します。登記簿謄本は、法人としての証明となるため、非常に重要です。
この流れをしっかり守ることで、スムーズに会社設立が完了します。
会社設立に必要な書類と準備物
会社設立にはさまざまな書類と準備物が必要です。必要な書類を揃えることが設立の第一歩となるため、しっかり準備をしましょう。以下で詳しく説明していきます。
必要書類のリスト
会社設立に必要な主な書類として、まず定款があります。定款は会社の設立時に必須であり、その内容が法的に適正であることを証明するため、公証人役場で認証を受ける必要があります。また、登記申請には、印鑑証明書や資本金払込証明書、役員の就任承諾書なども必要です。
その他に必要な書類を挙げてみましょう。
- 設立登記申請書
- 登録免許税分の収入印紙
- 発起人の同意書(発起人決定書、発起人会議事録)
- 設立時代表取締役の就任承諾書
- 監査役の就任承諾書
- 発起人の印鑑証明書
- 登記用紙と同一の用紙
印鑑証明書と資本金払込証明書、役員の就任承諾書は登記申請に必要な書類です。
これらの書類を一つずつ準備し、設立手続きが順調に進むようにしましょう。
書類の取得方法と作成時の注意点
書類の取得方法については、例えば定款は自分で作成して公証人役場で認証を受けますが、印鑑証明書は役員が住民票のある市区町村役場で取得します。資本金払込証明書は、会社設立前に指定した銀行での払込み証明が必要です。これらの書類を作成する際は、誤字や内容の不備がないか十分に確認し、法的に問題のないものを作成することが大切です。詳細については、以下の記事をご覧ください。
自分で会社を設立するメリットとデメリット
会社設立を自分で進めることにはさまざまなメリットとデメリットがあります。それぞれのポイントを理解して、どのような形で進めるべきかを見極めることが大切です。以下で詳しく説明していきます。
メリット:費用を抑えられる、手続きの流れを理解できる
自分で会社を設立する最大のメリットは、費用を抑えられる点です。専門家に依頼すると、その費用がかかりますが、自分で手続きすればその分節約できます。また、会社設立の一連の流れを自分で進めることにより、会社設立に関する知識を深めることができ、今後の経営にも活かせるでしょう。
デメリット:手続きが煩雑、ミスが発生するリスクがある
一方で、デメリットとしては手続きが煩雑である点です。特に初めて設立を行う場合、法的な知識が不足していると、ミスや不備が発生するリスクがあります。例えば、書類の記載内容に誤りがあった場合、登記が拒否されることもあります。そうしたリスクを避けるためには、事前に十分な準備をしておくことが重要です。
会社設立にかかる費用と節約方法
ここでは、会社設立にかかる費用と節約方法について解説します。会社設立にはさまざまな費用がかかりますが、その内訳や節約方法を知ることで、無駄な支出を減らすことができます。以下で詳しく説明していきます。
会社設立にかかる費用
会社設立にかかる費用を会社形態別に確認してみましょう。
株式会社
株式会社設立にかかる費用は次のようなものです。
- 定款の認証手数料:1.5万~5万円(紙と電子で同一)
- 定款用の収入印紙代:4万円(紙)※電子定款の場合は0円
- 定款の謄本手数料(250円×ページ数):2,000円程度(紙と電子で同一)
- 登録免許税:15万円~(※1:資本金額×0.7%、または15万円のどちらか高い方)
- 実印の作成代:約3,000円~
- 印鑑証明書代(約300円×枚数):300円~
- 登記事項証明書(登記簿謄本)発行費(約500円×枚数):約500円~
- 資本金:1円~
合同会社
合同会社設立にかかる費用は次のようなものです。
- 定款の認証手数料:ー
- 定款用の収入印紙代:4万円(紙)※電子定款の場合は0円
- 定款の謄本手数料(250円×ページ数):ー
- 登録免許税:6万円~(※2資本金額×0.7%、または6万円のどちらか高い方)
- 実印の作成代:約3,000円~
- 印鑑証明書代(約300円×枚数):-
- 登記事項証明書(登記簿謄本)発行費(約500円×枚数):約500円~
- 資本金:1円~
会社設立の手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合は、別途報酬費用が発生します。その報酬の目安は10万円くらいです。会社設立後に顧問契約をしてくださいと求められることもありますが、その場合は代行費用が無料になることもあります。
会社設立の手続きを代行できる専門家を紹介しましょう。司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士などの士業の方々です。それぞれの専門家でどんなことができるのか確認してみましょう。
▶登記申請
| 手続き | 代行依頼ができる専門家 |
| 定款作成 | 司法書士、行政書士 |
| 定款認証(公証役場) | 司法書士、行政書士 |
| 設立登記申請(法務局) | 司法書士 |
▶登記後の申請
| 手続き | 代行依頼ができる専門家 |
| 税金関係届出(税務署) | 税理士 |
| 社会保険関連届出(年金事務所) | 社会保険労務士 |
| 労務関係届出(労働基準監督署) | 社会保険労務士 |
| 雇用保険関係届出(ハローワーク) | 社会保険労務士 |
| 許認可届出(業種による) | 司法書士、行政書士※有料職業紹介事業、労働者派遣事業の許可申請は社会保険労務士のみ対応可能 |
参照:会社設立にかかる費用は?必須費用から節約方法まで徹底解説
登記申請費用や定款認証費用の詳細
登記申請には、定款認証費用や登録免許税が含まれます。定款認証には公証人手数料がかかり、登録免許税は法人登記の際に支払う必要があります。これらの費用は、設立時に必ず発生しますが、事前に計画しておけば、余計な出費を防げます。
電子定款を利用した印紙税の節約方法
印紙税は、定款に貼る印紙のことを指し、通常、4万円かかりますが、電子定款を利用すれば、この印紙税を節約することができます。電子定款を利用することで、定款を電子化し、印紙代を節約することが可能です。これにより、設立にかかる費用を大幅に削減できるため、積極的に活用するのが賢明です。詳細については、以下の記事をご覧ください。
参照:会社設立にかかる費用は?必須費用から節約方法まで徹底解説]
自分で会社設立を成功させるためのポイント
ここでは、自分で会社設立を成功させるためのポイントについて解説します。これらのポイントを抑え、計画的に進めることで会社設立が成功する可能性が高まるでしょう。以下で詳しく説明していきます。
スケジュール管理の重要性
会社設立は、時間的に余裕を持って進めることが成功の鍵です。スケジュールを立て、各ステップにどれだけの時間がかかるのかを把握しておきましょう。定款の作成や登記申請には一定の時間がかかるため、余裕をもって手続きを進めることが、スムーズな設立を実現します。
書類作成時に注意すべきポイント
書類作成の際は、記載内容が正確であることを最優先にしましょう。特に定款の内容は、会社設立後も重要な役割を果たすため、後で修正するのが難しい点があります。細部まで確認し、専門的な知識が必要な場合は調査を怠らないようにしましょう。
よくあるミスとその回避策
会社設立でよくあるミスには、定款の内容不備や書類提出期限の過ぎた申請があります。これらを避けるためには、事前に十分な確認を行い、締め切りを守ることが大切です。
まとめ
本記事では、会社設立の方法について基本的な流れや必要となる書類、自分で会社を設立するメリット・デメリットについて解説しました。会社設立は自分で行うことが可能ですが、しっかりと準備をし、計画的に進めることが求められます。もし不安や疑問があれば、専門家に相談することも一つの選択肢です。まずは、手続きの流れを理解し、必要書類をきちんと準備することから始めましょう。
FLAGSグループは、名古屋市で50年以上にわたり中小企業の成長を支援してきた豊富な実績を誇ります。会社設立に関するあらゆるサポートを提供しており、税理士、司法書士、社会保険労務士などの若手専門家が集結しています。税務署や各自治体への開業届出、労務関係の手続きなど、法人設立に必要な業務をワンストップでサポートします。
さらに、設立後の税務対策や相続税対策についても、丁寧にサポートいたします。法人化を検討中の方や、事業の拡大を目指している方は、ぜひFLAGSグループにご相談ください。将来の成長を見据えた適切なアドバイスと、手厚いサポートをご提供します。


2025.05.21