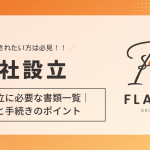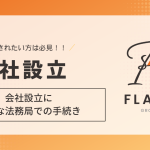COLUMN経営コラム

COLUMN経営コラム

会社設立にかかる期間は?手続きの流れと短縮のコツ
投稿日:2025.01.28
更新日:2025.01.28
経営
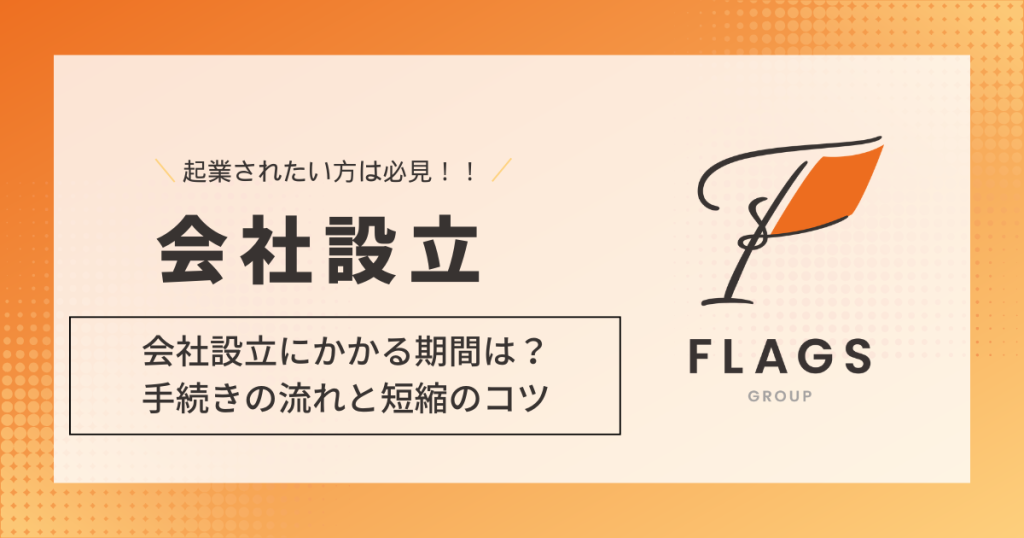
会社を新たに立ち上げることは、大きな決断です。事業の構想を練り上げ、形にしていく過程では、さまざまな手続きや準備が必要となります。そして、実際に会社を設立するには、定款の作成や資本金の払込、法務局への登記といった具体的なステップを踏まなければなりません。会社設立の手続きには一定の時間がかかり、その期間をどの程度見込むべきかを知らないと、不安が大きくなることもあるでしょう。
そこで本記事では、会社を設立する際に要する全体の期間やステップごとの所要時間を整理し、スムーズに進めるためのポイントをわかりやすく解説します。自分で進める場合と専門家に依頼する場合の違いや、会社設立後に必要となる各種手続きもあわせて確認し、全体を通して円滑に準備を進められるようにしましょう。
会社設立を目指す方にとって、この記事が少しでも不安を軽減し、実りある第一歩を踏み出すお手伝いになれば幸いです。
▼ この記事の内容
会社設立にかかる全体の期間とは?
会社設立にかかる全体の期間は、一般的に2~3週間ほどといわれることが多いです。ただし、この期間はあくまでも目安であり、書類の準備状況や認証手続きの混雑状況、専門家に依頼するかどうかによって前後します。
特に起業に慣れていない方や書類のやり取りに時間がかかる場合は、さらに期間が延びることも考えられます。
逆に、必要な書類を迅速に用意でき、電子定款などを活用して効率よく作業を進められる場合は、想定よりも早く設立手続きを終えられるかもしれません。以下で詳しく説明していきます。
会社設立の全体の流れ
会社設立の全体の流れは、大きく分けると定款内の必要事項の決定、定款の作成と認証、資本金の払込、法務局への登記申請というステップに整理できます。
最初に会社の基本事項を具体的に固める段階として、会社の名称や事業目的、資本金の額、役員構成、事業年度などを決定します。
その後、決定事項を踏まえて定款を作成し、公証役場での認証を受けます。認証が完了したら、資本金の払込手続きを行い、払込が完了したことを確認しながら登記申請書類を作成し、法務局へ提出します。
そして法務局での審査を経て登記が完了すると、会社設立が公式に成立します。この流れをスムーズに進めるためには、事前に準備を整えておくことと、書類不備が生じないように細心の注意を払うことが重要です。
各ステップにかかる平均的な期間
各ステップで必要となる平均的な期間は、定款作成に必要な準備を含めた数日から1週間程度、公証役場での認証は通常は1日で完了しますが、混雑状況や予約のタイミングによっては多少ずれ込むこともあります。認証後にすぐ資本金の払込手続きを行い、確認作業を経て法務局への登記申請書類をそろえるまでに数日程度を見込むとよいでしょう。
登記申請から登記完了までの期間は一般的には5~7日前後とされていますが、法務局が繁忙期にあたると、さらに日数がかかる可能性もあります。こうしたステップごとの期間をあらかじめ把握しておくことで、必要以上に焦らず、確実に手続きを終えられるようになるはずです。
会社設立の各ステップごとの所要時間
ここからは、会社設立までの流れをもう少し細分化して、それぞれのステップごとにどのくらいの時間がかかるのかを整理していきます。会社設立手続きは基本的に順序立てて行われるため、どの手続きがどの段階において最優先となるのかをしっかり把握することが大切です。以下で詳しく説明していきます。
定款作成と認証にかかる時間
定款作成は会社の基本事項を定める大切な作業です。内容としては、目的・商号・本店所在地・発起人の情報・事業年度・機関設計など、多岐にわたります。これらをすべて洗い出し、誤字や不備がないように整えたうえで公証役場へ持ち込み、認証を受けます。
通常、公証役場での認証自体は30分から1時間程度で完了することが多いですが、公証役場の予約をとる必要があるため、その予約タイミング次第では若干の遅れが生じる可能性があります。それでも数日以内には完了するケースが多いため、スケジュールを組むうえでも比較的見通しを立てやすいステップといえるでしょう。
ただ、定款の内容にミスや不足があると再作成を余儀なくされ、時間を浪費する恐れがあるため、事前のチェックは入念に行いたいところです。
資本金の払込とその確認手続き
公証役場で認証を受けた定款をもとに、資本金を発起人名義の口座に払い込みます。現金で手続きをする場合もあれば、オンラインバンキングで行う場合もありますが、銀行に出向くにしてもさほど時間はかかりません。問題は払い込みが完了したことを証明するための書類を整えるステップです。
具体的には、通帳のコピーや振込明細を漏れなく準備し、定款認証後のタイミングで速やかに準備する必要があります。ここでも書類の扱いにミスがあると再提出を求められる可能性があるため、なるべく早めに確認を行うことが重要です。資本金の払込自体は日にちを要する作業ではありませんが、他の書類とセットで管理する都合上、全体の流れを止めないように意識しておく必要があります。
登記申請から完了までの期間
登記申請は会社設立の最終段階かつ最も重要なステップです。必要となる書類には、定款や設立登記申請書、資本金の払込証明書、役員に関する書面などが挙げられます。書類がそろったら法務局へ申請を行い、問題がなければ受理され、数日から1週間程度で登記が完了します。
もっとも、法務局の繁忙期や申請内容の不備が見つかったときは、完了までに時間を要する場合があるため注意が必要です。登記が完了すると会社として正式に成立し、法人としての活動がスタートします。
各手続きの詳細は「会社設立の流れを解説!必要な手続きと準備すべきポイント」内でも解説していますので、あわせてご覧ください。
会社設立期間を短縮するためのポイント
会社設立手続きには、どうしても一定の日数がかかります。しかし、いくつかのポイントを押さえることで、手続きをスムーズに進めたり、全体の期間を短縮できる可能性があります。ここでは、比較的簡単に実践できる工夫を紹介します。
電子定款を活用して印紙税を節約&手続き時間を短縮
会社設立時には紙の定款を用いて認証を受ける方法と、電子定款を利用する方法があります。電子定款を使用すると4万円の印紙税が不要になるうえ、公証役場とのやり取りも電子データで済ませられる状況が整いつつあるため、移動や書類準備の手間が軽減されることがあります。手
続きの早さに関しても、紙媒体と比べてやり取りの時間を短縮できるケースが多く、結果的に設立期間の圧縮にもつながるでしょう。
ただし、電子定款を扱うには電子認証に必要な機器やソフトウェアの利用が必要になる場合もあるため、自分で対応するのが難しいと感じるなら、専門家に依頼するとスムーズかもしれません。
書類の事前準備を徹底する重要性
定款の作成や登記申請書類の整備をする際に、内容の抜け漏れや不備があると、その都度修正したり再提出する必要が生じ、手間も時間も増えてしまいます。あらかじめ会社の概要や役員構成、印鑑証明などを整理しておき、スムーズに書類を作成できる状態にしておくことが大切です。
公証役場に行く際に必要な書類がすべて手元にそろっているか、印鑑証明書の期限が切れていないかなどを事前にチェックし、疑問点があれば早めに確認すれば、トラブルのリスクを減らせます。書類作成がスムーズに進めば、全体の手続き期間を短く抑えやすくなるはずです。
必要書類の漏れやミスを防ぐ方法
定款の内容や払込証明など、会社設立に関する書類は数が多く、細かい要件も設定されています。書類を作成・提出する段階で漏れやミスがあると何度も修正や再提出を求められ、時間が大幅にかかる恐れがあります。こうした事態を避けるため、チェックリストを作成して手続き完了までの流れを可視化すると効果的です。
例えば、役員の印鑑証明書が何通必要なのか、出資者の名義や資本金の金額に誤りがないかなど、ミスが起きやすい項目をあらかじめ洗い出しておくのも良い方法です。地道な作業ですが、日程が逼迫すればするほど、ちょっとした不備が大きく響くこともあるので、慎重な確認こそが時間短縮の鍵になります。
自分で進める場合と専門家に依頼する場合の違い
会社設立の手続きをすべて自分で行うか、それとも専門家に依頼するかは大きな分かれ道です。費用面や手続きの煩雑さ、手続きにかかるトータルの時間を考慮し、どちらの選択が自分に合っているかをよく検討する必要があります。以下で詳しく説明していきます。
自分で進める場合の所要期間と注意点
自力で会社設立手続きを行う場合、専門家に支払う報酬を抑えられるというメリットがあります。手続きそのものは法務局や公証役場が主たる窓口となり、ネット上でも情報が多く公開されているため、調べながら進めることは可能です。
しかし、情報を正しく理解して間違いなく書類を準備するには時間と手間がかかります。定款の書式や認証手続き、登記申請の記載内容など、細部を怠ると後で修正が生じることもあるでしょう。修正が多いほど、結果として想定以上の期間が必要になるため、スケジュールに余裕をもって取りかかることが求められます。
専門家に依頼する場合のスケジュール感
専門家に依頼する場合は、行政書士や司法書士、税理士といった会社設立に関わるプロが手続きを代行してくれるため、書類作成や認証、登記申請の手戻りが少なく、スピーディーに進むメリットがあります。専門家は必要書類を熟知しており、定款の内容にも精通していることが多いため、書類不備によるトラブルを最小限に抑えられます。
その結果、全体として日数の短縮につながることが期待できます。費用はかかるものの、経営者自身が事業の準備に専念できる点や、設立後の税務手続きや社会保険の届け出について相談しやすい点も魅力です。
各種手続きの詳細は「会社設立の流れを解説!必要な手続きと準備すべきポイント」内でも解説しているため、そちらも参考にしてみてください。
会社設立後に必要な手続きとスケジュール
会社設立が完了したら、すぐに事業をスタートできるわけではなく、さらにいくつかの手続きが必要です。スムーズに事業活動へ移行するためにも、これらの手続きとおおよその期間を把握しておきましょう。以下で詳しく説明していきます。
法人番号の取得と通知
会社を設立すると、国税庁によって法人番号が付与されます。この法人番号は登記完了後、通常1週間以内程度に登記上の所在地へ通知されます。法人番号は、税務手続きや社会保険の手続きにも広く使われるため、大切に保管しましょう。
通知が届いたら、すぐに番号を把握し、必要に応じて経理システムや事務書類へ反映させていくとスムーズです。法人番号は企業の識別情報として重要な役割を果たすため、事業で取引する際にも必要となることが多くあります。
税務署や社会保険事務所への届け出
設立後に行う主な手続きとして、税務署への法人設立届出書や給与支払事務所等の開設届出書、都道府県税事務所や市町村役場への各種届出が挙げられます。
さらに、従業員を雇用する場合は社会保険手続きも必要です。これらの提出書類には期限が定められているものがあるため、遅れが生じると罰則が科される可能性もあります。早めに提出できるよう準備リストを作成し、登記完了と同時に進められる項目はすぐに取りかかるのがおすすめです。
経営者自身が手続きを行う場合は時間を要するため、専門家に相談して各種届出をサポートしてもらうと安心です。
これらの手続きも「会社設立の流れを解説!必要な手続きと準備すべきポイント」で詳しく紹介しています。
まとめ
本記事では、会社を設立する際に要する全体の期間やステップごとの所要時間を整理し、スムーズに進めるためのポイントを解説しました。会社設立には、定款の作成から登記申請までの手続きにおいて一定の期間が必要となります。一般的には2~3週間程度が目安ですが、準備不足や書類不備があるとそのぶん日数が延びてしまうため、事前に流れを理解し、各ステップを着実に進めることが大切です。
また、会社設立の流れを熟知した専門家に依頼することで、手戻りを防ぎつつスケジュール管理がより容易になるでしょう。費用とのバランスを検討したうえで、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
FLAGSグループは、名古屋市にて50年以上にわたり、多くの中小企業の成長を支えてきた実績があります。法人設立に必要な手続きについて、税理士、司法書士、社会保険労務士など、専門的な知識を持つ若手プロフェッショナルが集まり、開業に関するさまざまなサポートを一貫して提供しています。具体的には、税務署や自治体への届け出、労務関係の手続きなど、法人設立に伴うあらゆる業務をスムーズにサポートいたします。
さらに、設立後の税務や相続税対策についても、将来を見据えた戦略的なアドバイスを行い、丁寧にサポートいたします。法人化をお考えの方や事業の拡大を目指す方にとって、FLAGSグループは信頼できるパートナーとなること間違いなしです。将来的な成長を見越した最適なアドバイスと、充実したサポート体制を提供いたしますので、ぜひご相談ください。