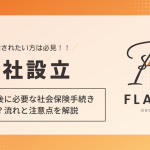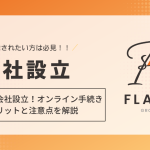COLUMN経営コラム

COLUMN経営コラム

会社設立と創業の違いは?意味と進め方をわかりやすく解説
投稿日:2025.04.30
更新日:2025.06.29
経営
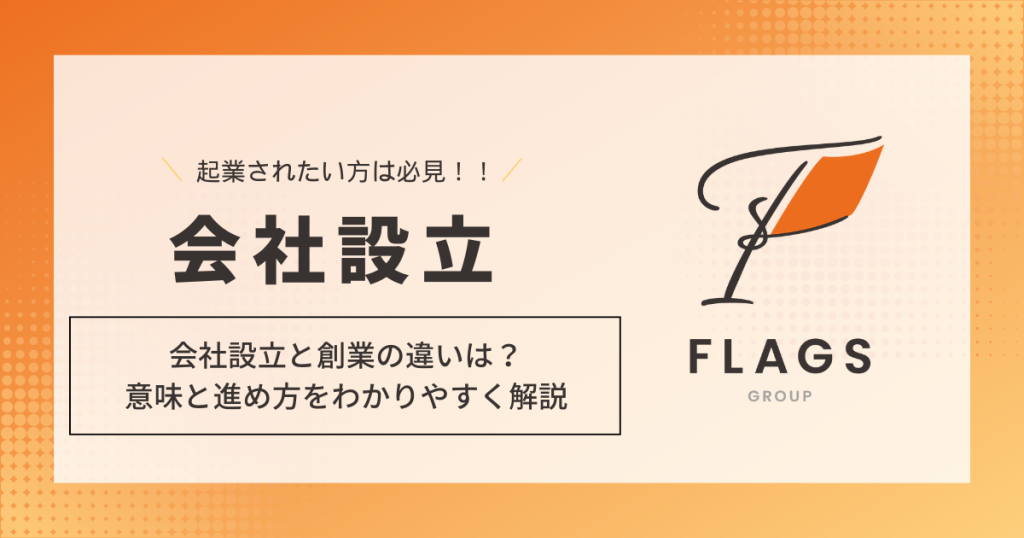
会社を設立する、創業するなど似たような用語がいくつかありますが、その違いをご存じでしょうか。いざ聞かれると、意外に違いを説明しにくいものです。
そこで今回は、各用語の違いを取り上げながら、法的な重要性や手続き方法などについて考えてみます。これから会社を興そうと考えている方はぜひ記事の内容を参考にしていただき、しっかり準備した上で臨んでください。
この記事の内容は、各分野のプロフェッショナルが在籍する団体が執筆を行っております。確かな内容をまとめたものになるので、どうぞ安心してお読みになってください。
▼ この記事の内容
創業、開業、設立、創立、起業の違い
会社を始めることを意味する言葉には、次のようなものがあります。
- 創業
- 開業
- 設立
- 創立
- 起業
皆さんはこれらの用語の違いについて考えたことはありますか。普通はそれぞれの用語の違いをあまり意識しないのではないでしょうか。
そこでまずこれらの用語の違いを確認しておきましょう。
大きく創業と起業に大別される。創業と起業の違いは、言葉が使用される時期による
上記で取り上げた用語(言葉)を大きく分けてみると、創業と起業の2つに集約されます。創業には、開業、設立、独立、創立などの言葉が含まれるといっていいでしょう。
では、創業と起業でどのような違いがあるのかというと、言葉が使用される時期によります。簡単にそれぞれの概要をまとめてみましょう。
| 創業 | 起業 |
| 全ての事業主を対象にした言葉であり、事業を始めた後に用いる | 事業を始める前に用いる |
事業を始めた後に用いるのが創業という言葉で、創業した人を創業者と言います。つまり過去の行動を基準にした言葉ということです。
起業は事業を始める前に用いる言葉なので、事業をすでに始めた人を起業者とは言いません。
創業といった場合は、対象者は全ての事業主で、個人事業主も法人も含まれます。その言葉が主に意味するところは、会社を始めるためのアイデアやビジネスモデルを構築したということになります。
創業に含まれる各用語の説明もしておきましょう。
| 開業 | 設立 | 独立 | 創立 |
| 具体的な店舗や事業所を構えて、事業を始めること 主に小売業やサービス業など、顧客と直接接する業種で用いられる言葉 | 法的手続きや登記関連で用いられる言葉 法人化することが目的で、法人のみが対象 | 自分でビジネスを経営し、他人に頼らずに生計を立てること | 組織としての事業を始めたことを意味する言葉 |
開業
開業というと、お店や事業所を新たに開いて、接客やサービス提供をスタートさせるという意味合いでよく使われます。どちらかというと商売色の強い言葉で、飲食店や小売店などを対象に用いられることが多いです。
開業は個人事業主を対象に用いられることが多い言葉であり、法人に関しては開業とはあまり言いません。「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類もあります。
設立
設立という言葉は、法的手続きや登記関連でよく用いられます。株式会社や合同会社を起こして、登記をするときなどです。
個人が事業を始めたときは普通開業と言いますが、会社を初めて登記することになると設立ということになるでしょう。
一度会社を設立した後、同じ人がまた別の会社を作った場合も、その都度設立したことになります。
独立
独立とは、依存関係にあった会社などから離れ、自分でビジネスを起こして経営し、他人に頼らずに生計を立てるときに用いられる言葉です。自分のスキルや経験に自信がある人はそのスキルと経験を活かした事業を興し、独立することがよくあります。
独立は創業や設立の前段階といってもいいでしょう。
創立
創立とは、組織や機関、団体などを新たに始める際に用いる言葉です。必ずしも会社だけには限りませんが、個人事業主には当てはめられない言葉です。
創立のポイントは、新たに、初めて起こすという点です。すでにある会社を分社化して子会社を作り、そこで別の事業を始めた場合は、初めてには当たりませんから、創立とは言いません。
事業のステージに応じた選択が重要である
新たな事業を興すことに関連する様々な用語(言葉)の解説をしましたが、理解できたでしょうか。
それぞれの言葉について言うと、事業のステージに応じた選択をすることも重要になってきます。たとえば、創業から設立へのステップを考えてみましょう。
事業を始めた段階では創業となりますが、事業が拡大して、法人化が必要になると設立に進む必要も出てくるでしょう。事業規模の拡大につれて、リスク管理や資金調達のための方策も考えないといけなくなってきますが、その手段の一つが法人化です。ここで設立に進むことになるでしょう。
事業計画書やプレゼンテーションなどの公式の場では、使い分けた方が良い
創業、開業、設立、創立、起業などの言葉を特に意識して分けずに使用する人もいます。それほど重要な場でなければ、それでも問題はありません。厳密に分類する必要がないケースもあるでしょう。
しかし、事業計画書やプレゼンテーションなどの公式の場では、使い分けた方が良いですね。それぞれの言葉の正確な意味が違う以上、正式な場では混同して使うのは好ましくありません。
自分にとっても相手にとっても誤解が生じないように、一つ一つの言葉を間違えのないように使いましょう。
会社にとって法的に重要なのは創業日?設立日?
創業と設立の意味はすでにお分かりになったでしょうが、それぞれには創業日、設立日というものもあります。
この創業日と設立日、会社にとってどのような意味合いがあり、法的にはどちらが重要なのでしょうか。考えてみましょう。
設立日である
会社にとって法的に重要なのは、設立日の方です。創業というと新しく事業を始めただけの意味しかありませんが、設立には法的な意味合いがあるからです。
設立日といった場合、設立登記によって法人格を取得し、法人としての権利・義務が発生する日としての意味があります。設立日=法人登記申請日です。法務局が開いている平日に申請を行うことになります。
設立日を選ぶ際は、注意点もあります。
まず設立日はあくまでも法務局に登記書類を提出した日であり、登記完了日を意味するものではないことは覚えておいてください。登記完了日は、申請書類に不備がなければ1週間から10日後程度になります。登記の効力が発生するのは登記申請書の提出日まで遡ります。
少しわかりづらい点かもしれませんが、間違わないようにしましょう。
登記申請書類の提出方法と会社設立日
登記申請書類の提出方法は3種類あり、それぞれの会社設立日は以下のようになります。
| 登記申請書類の提出方法 | 会社設立日 |
| 窓口提出 | 申請した日 |
| 郵送提出 | 書類が到着した日 |
| オンライン提出 | 申請が受理された日(システムトラブルなどがなければ、基本的に申請した日になる) |
設立日によって法人住民税均等割の負担金額が変わる
法人住民税とは、法人の事務所が位置する地方自治体に納めなければいけない地方税です。法人住民税は法人税割と均等割で成り立っています。それぞれの概要と、設立日との関係を見てみましょう、
法人税割
法人住民税の法人税割は法人税の税額をベースに算出されます。計算式は以下のようになります。
「法人税割=法人税額×税率」
こちらは会社設立日とは関係なく、あくまでも法人税額や会社規模と地方自治体ごとに定められた税率が基準になります。
均等割
法人住民税の均等割は法人の資本金額や従業員数などをベースに算出される地方税です。こちらは課税所得には関係なく課される税金であるため、赤字決算でも納税しないといけません。
設立日と関係があるのは均等割の方です。均等割の計算では、会社の事務所がその自治体にあった月数に応じて年間の税額が月割計算されます。ここまではいいですね。
ここからがポイントで、1ヶ月のうち1日でも欠けている月があると、その月は切り捨てになるのです。つまり、1ヶ月分の均等割が無しということです。
例を挙げてみましょう。会社の設立日が8月15日で、決算日が翌年3月31日だとします。この間の月数は正確に言うと、8ヶ月です。しかし、3月15日から3月31日までは17日間しかありません。つまり、本来の月数に満たないのです。この場合は、切り捨てになりますから、実際に均等割を納めるのは7ヶ月分ということになります。
このように設立日のよって住民法人税の均等割の納税額が変わるので、設立日がいつになるのかは非常に重要です。
創業日は、開業届の提出や法人登記の有無を問わず事業を始めたタイミングを指す
創業日は開業届を提出した日や法人登記をした日とは関係のない日になります。つまり、法的な意味合いがない日になるので、設立日ほどの重要性はないと言えます。
創業日と設立日が一致しないケース
創業日と設立日が一致しているケースもありますが、それぞれ意味の異なる言葉なので、一致しないこともよくあります。では、どんなケースで一致しないのかを確認してみましょう。
創業と設立では意味が異なるので、会社の概要や沿革の紹介で使い分けることがある
各会社で意味の異なる創業と設立を概要や沿革紹介で使い分けることがあります。
まず、創業時に法人制度がある場合を見てみましょう。この場合は、個人事業主として創業し、その後で法人化できます。そうなると、個人事業主として事業を開始した日が創業日で、法人化した日が設立日となるでしょう。そのような例を挙げてみましょう。
ただ、実際に個人事業主から法人成りした方の企業名はわからないので、業種のみを紹介します。
- 内装工事業A社:個人事業主として仕事を請け負っていたが、所得も非常に大きくなっていたので法人化した
- ホームページ制作B社:元々個人事業主であったが、他の人と一緒に仕事をすることになり法人化した
いずれのケースも事業を始めた創業日と法人化した設立日が異なっています。
次は創業時に法人制度がない場合です。室町時代や江戸時代に創業された老舗企業が該当します。
この場合、初代が商売を始めたと伝えられる日が創業日です。そして、現代になり、法人制度ができてから法人化した日が設立日となるでしょう。事例を挙げてみます。
- 高島屋:創業日は1831年で、設立日は1909年
- YAMAHA:創業日は1887年で、設立日は1897年
創業日と設立日が一致するケース
創業日と設立日が一致するケースでは、会社資料に設立日だけ記載しておけば十分です。
個人の創業には開業届の提出、会社の設立には5ステップの手続きが必要
ここからは、個人が創業する場合と会社を設立する場合の手続き方法を説明します。
個人の創業
個人の創業手続きと、そのメリット・デメリットを見てみましょう。
基本的には、税務署に開業届を提出するだけ
個人の創業手続きは簡単です。税務署に開業届を提出するだけで開業はできます。
ただ、これだけで創業した事業がうまくいくわけではありません。やらなければいけないことがいろいろあります。簡単にまとめておきましょう。
- アイデアの発想:顧客のニーズに対応し、競合他社と差別化された商品やサービスを提供するようなアイデアを考える
- 事業計画の作成:ビジネスの目標や戦略、収益予想などを明確に記述した文章で事業の方向性や将来像を示す
- 資金調達:資金調達方法は多様。各方法のメリット・デメリットを把握し、行っている事業に適した資金方法を選ぶ
- 事業の立ち上げ
- 事業運営と成長
創業のメリット
個人が創業するメリットは、次のようなことです。
- 自分のアイデアやビジョンを実現できる
- 独立して働くことで、自由な働き方ができる
- 自分の努力次第で利益を上げられる
- 自分でチームを組織し、リーダーシップを発揮できる
- 新しい市場の開拓、技術の錬磨などを図れるチャンスが広がる
創業のデメリット
個人が創業するデメリットは次のようなことです。
- 収入が不安定になりやすい
- 重い経営責任が肩に掛かってくる
- 事業が失敗したときのリスクがある
- 長時間労働になったり、大きなストレスが溜まったりすることがある
- 資金調達で苦労することがある
会社の設立
続いて、会社設立のステップやメリット・デメリットを解説します。まずはステップからです。
1.事業計画書を作成する
最初に設立の目的や理由を明確にしたうえで事業計画書を作成します。
2.設立するための事前準備を行う
次に会社設立の準備として、印鑑を用意したり、法人形態を選択したり、役員選任を行ったりします。法人形態の選択は事業規模や目的に応じて行ってください。
3.定款を作成し、認証を受ける
会社を設立するときは、定款を作らないといけません。定款は会社の憲法とも呼ばれる基本的なルールを定めたものです。定款には次のような項目を盛り込みます。
- 会社概要
- 発行可能株式総数
- 株式の譲渡制限
- 役員の選任方法など
定款には紙の定款と電子定款があります。紙の定款では、手続き時に収入印紙代として4万円掛かります。電子定款には印紙代は必要ありません。
定款を作成後、認証手続きに移りますが、2つのパターンがあります。まず株式会社の場合は作成した定款を公証役場に提出しましょう。合同会社の場合は、定款認証が不要です。
4.資本金を払い込む
続いて、資本金を払い込むのですが、株式会社でも合同会社でも資本金の額は1円でも構いません。1円で会社設立ができます。ただ、資本金の額が極端に少ないと、事務所を借りるための敷金・礼金や備品購入費が不足する恐れもあります。
そのため、最低限の資本金として、初期費用+運転資金3ヶ月分くらいは用意しておきたいところです。
5.登記申請書類を作成し、申請する
会社設立でも非常に重要な場になるのが登記申請書類の作成と申請です。作成・提出する書類は会社形態によって変わることがあります。
設立登記申請書や定款、資本金の払い込みを証明する書類などは、株式会社にも合同会社にも共通して必要です。
法人登記の申請を行った日が会社設立日になります。特定の日を会社設立日にしたい場合は、その日に合わせて登記申請を行いましょう。
なお、登記手数料という費用も掛かります。
設立のメリット
会社設立のメリットは次のようなことです。
- 法人格の取得による信用向上
- 責任が限定される
- 税制上の優遇措置を受けられる
- 資金調達がしやすくなる
設立のデメリット
会社設立のデメリットは次のようなことです。
- 手続きが面倒で、費用が掛かる
- 法人税負担が増加することがある
- 決算や税務申告が複雑になる
- 役員や株主への報告義務と責任が生じる
- 事業を閉鎖するときにやりにくくなる可能性がある
まとめ:創業と設立の違いやメリット・デメリットを詳しく知りたい場合は専門家に相談を検討
今回は、創業や設立など、事業開始時に使われる言葉の意味の違いや法的重要性、創業や設立の手続き・メリット・デメリットなどを解説しました。事業開始時に使われる言葉はいろいろありますが、それぞれの意味の違いを把握したうえで使うことでスムーズな事業展開もできるようになるでしょう。
ただ、上記の詳しいことになると、素人ではわからないこともあります。そのようなときはぜひ専門家に相談してみましょう。専門家なら各言葉にも通じているし、手続きのやり方なども詳しいですから、とても頼りになります。