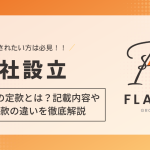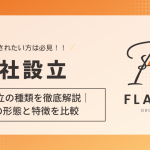COLUMN経営コラム

COLUMN経営コラム

会社設立を活用した相続税対策とは?メリットと注意点を解説
投稿日:2024.12.25
更新日:2024.12.25
税務経営
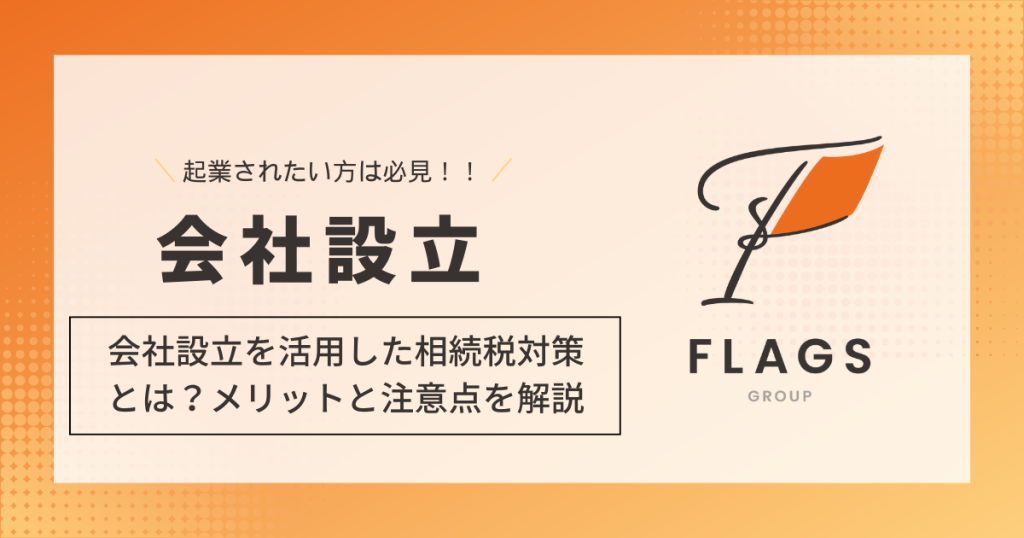
相続税は、遺産を引き継ぐ際に避けては通れない重要な課題の一つです。特に資産規模が大きい場合や事業承継を伴う場合、適切な相続税対策を行わなければ、想定以上の税負担が発生する可能性があります。そんな中、会社設立を活用した相続税対策が注目されています。法人化を通じて資産を分散させたり、相続税評価額を引き下げたりすることで、大きな節税効果を得ることができるのです。
しかし、会社設立を利用した相続税対策にはメリットだけでなく、費用や運営上のリスクも伴います。また、この方法がすべてのケースに適しているわけではありません。そのため、他の相続税対策との比較や、具体的な事例を通じて効果を検討することが重要です。
この記事では、会社設立による相続税対策の具体的な方法やメリット・注意点、さらには実際の活用例までを詳しく解説します。専門家のアドバイスを活用した対策の重要性にも触れながら、最適な相続税対策のヒントをお届けします。
▼ この記事の内容
会社設立を活用した相続税対策とは?
会社設立は、単なる事業の開始や法人格の取得にとどまらず、相続税対策としても非常に有効な手段です。特に、資産を管理するための法人化は、相続税負担を軽減し、財産のスムーズな承継を可能にします。ここでは、相続税の仕組みや法人化による具体的な効果について詳しく解説します。
相続税の仕組みと負担の現状
相続税は、被相続人が死亡した際に、その財産を承継した相続人に課される税金です。課税対象となる財産には、現金、預金、不動産、株式などが含まれます。相続税率は累進課税方式を採用しており、財産規模が大きくなるほど税負担が重くなります。
近年、都市部を中心に地価が高騰していることもあり、不動産を多く所有する家族では、現金化が難しい資産で相続税を支払わなければならないケースが増えています。
また、基礎控除額の引き下げにより、課税対象者の範囲が広がったことも影響しています。これらの背景から、相続税対策が求められる状況が顕著になっているのです。
会社設立が相続税対策に活用される理由
会社設立が相続税対策として注目される理由には、法人を通じて資産管理を行うことで、資産の分散や相続税の評価額を引き下げられる点にあります。さらに、法人化することで、相続財産を明確に管理できるようになります。これにより、親族間の紛争を未然に防ぎ、財産承継が円滑に進むという利点もあります。
法人化による資産の分散や評価額引き下げの効果
法人化が相続税対策に効果的である理由として、資産の分散や評価額の引き下げが挙げられます。たとえば、不動産を個人名義から法人名義に変更すると、不動産の相続税評価額が路線価ベースで計算されるため、市場価値よりも低く評価されることがあります。これにより、相続税額を大幅に削減できる可能性があります。
さらに、資産管理会社を設立し、家族を役員にすることで、給与や賞与を通じて所得を分散させることができます。この方法は、所得税の累進課税を回避する手段としても有効です。また、法人化した資産は分割しやすくなるため、親族間での資産配分がスムーズに進む利点もあります。
法人化によるこれらの効果を十分に引き出すためには、適切な設計と運用が不可欠です。そのため、事前に専門家のアドバイスを受けることが重要となります。
会社設立による相続税対策のメリットとデメリット
会社設立を活用した相続税対策は、多くのメリットが期待されますが、一方で注意すべきポイントも少なくありません。ここでは、メリットと注意点を整理し、どのようなケースで適しているのかを詳しく説明します。以下で詳しく説明していきます。
会社設立による相続税対策のメリット
会社設立を活用する最大のメリットは、相続税負担の軽減です。法人を通じて資産を管理することで、資産の評価額を抑え、結果的に相続税を低減できます。特に不動産や株式の評価額は、個人で所有する場合と比較して法人名義にすることで低く見積もられることがあります。
また、会社設立により、資産管理が効率化します。法人化された資産は、一元的に管理できるため、財産の分配や運用計画が立てやすくなります。これにより、親族間での意見の衝突を未然に防ぐことが可能となり、スムーズな資産承継が期待されます。
さらに、法人化することで節税効果も得られます。たとえば、家族を役員にして給与を支払うことで、所得分散を図ると同時に、経費として認められる範囲が広がります。この仕組みを活用すれば、相続税だけでなく、所得税や住民税の負担も軽減できます。
会社設立による相続税対策のデメリット
一方で、会社設立には初期費用や運営コストがかかる点に注意が必要です。設立時には登記費用や定款の作成費用が必要であり、さらに毎年の法人税や顧問税理士費用などのランニングコストも発生します。
また、法人化に伴い、税務上のリスクが増加する可能性があります。不適切な運用や税務申告のミスにより、追加課税や罰則を受けるリスクがあるため、専門家のサポートが欠かせません。
さらに、法人設立後は、適切な資産管理が求められます。不動産や金融資産をどのように管理し、役員報酬や配当をどのように設定するかは、税務的な影響を慎重に考慮する必要があります。これらの要素を見誤ると、当初期待していた節税効果が十分に発揮されない可能性があります。
会社設立が向いているケース
会社設立による相続税対策が特に適しているのは、資産規模が大きい場合や事業承継を計画しているケースです。
たとえば、大規模な不動産を所有している家庭では、法人化を通じて資産評価を下げることが可能です。また、事業承継においても、法人を活用することで、次世代への事業引き継ぎがスムーズに行えます。この方法は、経営権を家族内で維持しながら、相続税負担を軽減するための有効な手段として広く利用されています。
会社設立を活用した相続税対策の具体例
ここでは、会社設立を通じた相続税対策の具体例を紹介します。具体的な活用方法を知ることで、会社設立の効果をより深く理解できるでしょう。以下で詳しく説明していきます。
資産管理会社の設立で評価額を引き下げた例
ある家庭では、多額の金融資産を所有しており、そのままでは高額な相続税が課される見込みでした。しかし、資産管理会社を設立し、資産を法人名義に移すことで、評価額を引き下げることに成功しました。結果として、相続税負担が大幅に軽減され、資産運用の効率も向上しました。
家族を役員にして給与を分散した例
別の家庭では、法人を設立して家族全員を役員として登録しました。その後、役員報酬を各人に分配することで、所得税の負担を軽減すると同時に、相続税対策も実現しました。この方法により、所得の累進課税率を抑えることができ、全体の税負担が減少しました。
不動産管理会社の設立で相続税評価額を軽減した例
不動産を多く所有する家庭では、不動産管理会社を設立し、不動産を法人名義に変更しました。この結果、相続税評価額が路線価で算定され、実際の市場価格よりも低く評価されました。この手法により、大幅な節税を達成するとともに、不動産の管理が効率化されました。
会社設立の流れと必要な手続き
会社設立を進める際には、商号の決定や定款の作成、登記手続きなど、いくつかの重要なステップがあります。また、必要な書類や費用についてもあらかじめ把握しておくことが大切です。
詳しい流れや手続きについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
他の相続税対策との比較
相続税対策にはさまざまな方法があり、会社設立を含む複数の選択肢を適切に組み合わせることで、より効果的な節税を実現することが可能です。ここでは、会社設立以外の代表的な相続税対策方法について詳しく説明し、それぞれの特徴と会社設立との組み合わせによるメリットを考察します。
生前贈与や生命保険を活用した方法
生前贈与は、相続税対策として非常に有効な手段です。相続開始前に財産を贈与することで、相続財産の額を減らし、相続税の課税対象を減少させることができます。特に基礎控除や贈与税の非課税枠を上手に活用することで、相続税を減らすことが可能です。また、贈与契約をきちんと結ぶことで、将来的な紛争を防ぐ効果も期待できます。
生命保険を利用する方法も相続税対策として一般的です。生命保険の保険金を受取人に指定し、その金額を非課税枠内で受け取ることができます。この方法は、相続税負担を減らすための手段として、特に現金や現物財産が少ない場合に有効です。ただし、生命保険契約に関しては保険金額や契約内容を慎重に選ぶ必要があります。
生前贈与や生命保険は短期間で効果を発揮する点が魅力ですが、同時に贈与税や生命保険料の支払いが必要となるため、コスト面も考慮しなければなりません。これらの方法と会社設立を組み合わせることで、より多角的な節税対策を講じることができます。
不動産購入や資産の移転
不動産購入や資産の移転も、相続税対策において有効な手段の一つです。不動産は、相続時に評価額が引き継がれますが、事前に購入しておくことで、評価額を低く抑えることができる場合があります。特に、賃貸不動産を購入しておくと、実際の資産価値と相続時の評価額に差が出るため、評価額を引き下げる効果が期待できます。
また、資産を移転する方法としては、名義変更を行ったり、複数の名義人を設定したりすることが考えられます。これにより、資産が分散され、相続税の負担を軽減することができます。しかし、資産の移転には慎重な計画が必要であり、無理な移転や遺言の不備があれば後々トラブルの原因にもなりかねません。
不動産購入や資産の移転と会社設立を組み合わせることで、より効果的な相続税対策が可能です。たとえば、不動産を法人名義に移すことで、評価額を低減させ、相続税の負担を軽減することができます。会社設立と組み合わせることにより、資産管理が効率化され、相続時の手続きもスムーズに行えるようになります。
会社設立との併用が有効な場合
会社設立を相続税対策の手段として単独で利用するだけでなく、他の方法と併用することで、相続税の軽減効果をさらに高めることができます。例えば、前述の生前贈与や生命保険と組み合わせることにより、相続財産を減らしつつ、法人設立を通じて資産の評価額を引き下げることができます。
また、不動産購入や資産移転と併用することで、法人を活用した資産の分散が可能になります。法人化することにより、個人名義での不動産所有よりも評価額が低くなるため、相続税の負担を軽減できるのです。このように、会社設立は他の対策と併用することで、さらに強力な節税策となります。
会社設立や相続税対策を専門家に相談するべき理由
相続税対策や会社設立に関する手続きは、非常に複雑で専門的な知識が求められます。そのため、税理士や行政書士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、相続税法や税務上の手続きに精通しており、適切なアドバイスを受けることで、最適な節税対策を行うことができます。
税理士や行政書士の役割
税理士は、税の専門家として相続税に関する法律や規制に精通しており、適切なアドバイスを提供してくれます。相続税は、相続財産の評価や申告手続き、納付に関して非常に複雑な部分が多いため、税理士に相談することで、ミスなく手続きを進めることができます。また、行政書士も、相続に関する書類作成や登記手続きなどをサポートするため、適切な法的手続きを実現できます。
さらに、税理士や行政書士は、相続税対策だけでなく、事業承継や法人設立に関してもサポートを提供してくれます。これにより、相続税対策と同時に、事業の継承に関する問題も解決できるため、総合的なアドバイスを受けることができます。
複雑な税制や法律を正確に理解するための専門家の重要性
相続税法や税制は頻繁に改正されるため、常に最新の情報を把握している専門家に相談することが非常に重要です。税制の変更や新たな優遇措置を逃さないためにも、専門家の助言が不可欠です。また、税理士や行政書士は、税制の複雑さを分かりやすく説明してくれるため、素人には難解な税法の理解を深めることができます。
専門家の支援を受けることで、法律や税制に関する誤解を避け、適切な相続税対策を立てることができるため、最終的に高い節税効果を得ることができます。
相談のタイミング
相続税対策や会社設立に関しては、できるだけ早い段階で専門家に相談することが重要です。相続が発生した後では遅く、対策を講じることが難しくなります。そのため、事前に計画を立てて、相続税や事業承継に関する対策を行っておくことが肝要です。
特に、事業承継を考えている場合、事前に専門家に相談して、法人設立や相続税対策を組み合わせたプランを立てることが必要です。これにより、事業を次世代にスムーズに引き継ぐことができ、相続税負担を軽減することができます。
まとめ
本記事では、会社設立による相続税対策の具体的な方法やメリット・注意点などについて解説しました。会社設立を活用した相続税対策は非常に有効ですが、他の対策方法との併用により、その効果を最大限に引き出すことが可能です。早期に対策を始めることで、将来の相続に備えることができ、スムーズな資産承継が実現します。
会社設立による相続税対策について、具体的な相談やサポートが必要な場合は、専門家に相談することで、複雑な税制や手続きを適切に理解し、最適な節税対策を講じることができます。
FLAGSグループは、名古屋市で50年以上にわたって、中小企業の成長と安定をサポートし続けてきた実績を持ちます。税理士、司法書士、社会保険労務士、弁護士、中小企業診断士などの若手専門家がパートナーとして集結し、税務署や各自治体への開業届出、社員の雇用に伴う労務関係の届出など、法人設立に必要な手続きをワンストップでサポートします。会社設立をお考えの方や、相続税対策を検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。