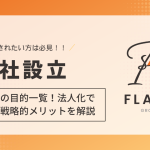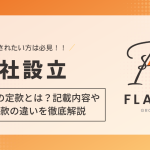COLUMN経営コラム

COLUMN経営コラム

会社設立の登記手続き完全ガイド!必要書類や費用、流れを解説
投稿日:2024.11.29
更新日:2024.11.29
経営
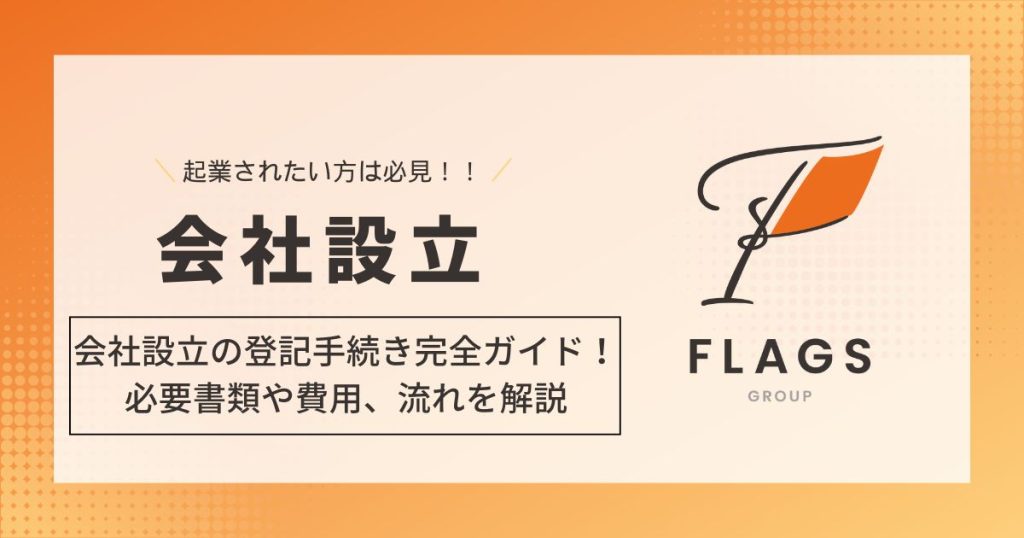
会社を新たに設立する場合に必要になる作業が登記です。法務局に登記申請をするのですが、初めての会社設立ともなると、どのように登記をするのかも分からないでしょう。そこで今回は、会社設立登記で準備する書類や手続きの流れ、かかる費用やその費用の節約方法、オンラインでの手続き方法、手続き相談先などを紹介します。これで登記手続きも支障なくできるようになるでしょう。
この記事は各分野のプロフェッショナルが在籍する団体が執筆を担当していますから、内容は確かなものです。安心して最後までお読みください。
▼ この記事の内容
会社設立における登記の重要性と準備するべきこと
画像引用元:写真AC
会社設立時に行わなければいけないのが登記ですが、その重要性がどこにあるのかを解説しましょう。また、登記をする際に準備するべきことも紹介します。
登記手続きの概要とその役割
会社設立登記を法人登記と言い、会社設立時に行うことが義務づけられています。会社法による規定です。
では、法人登記で何をするのかというと、次のような項目を法務局に登録し、一般に開示します。
- 会社名、あるいは商号
- 本店所在地
- 代表者の氏名と住所
- 事業目的など
法人登記を行うと、その証拠として、法務局から登記事項証明書が発行されます。これを持って、法人としての存在が法的に認められることになり、内外から信頼されるようになり、取引がスムーズに進むようになります。
登記を円滑に進めるための準備とスケジュールの立て方
登記を円滑に進めるためには、準備を万端整えて、適切なスケジュール設定をしなければいけません。
まず準備ですが、次のようなことを行っておく必要があります。
- 発起人を決める
- 会社の基本事項を決めておく(会社名<商号>、所在地、事業目的、資本金、会計年度など)
- 会社印を作成する
- 定款を作成して、認証を受ける
- 資本金を払い込む
- 必要書類を準備する(後ほど説明します)
次はスケジュール設定。登記申請してから、登記が完了するまで1週間ほど掛かります。会社設立自体に掛かる期間は⒉~3週間。
このスケジュールを把握した上で、会社設立に向けての作業を行わなければいけません。
法人化における登記と個人事業主との違い
法人登記された会社と個人事業主との間では大きな違いがあります。次の表を見てください。
| 個人事業主 | 法人 | |
| 1.事業開始までの手続き | 開業届を税務署に提出青色申告を希望する人は「青色申告承認申請書」も提出 | 法務局での法人登記会社設立に必要な書類や会社印の用意が必要 |
| 2.事業開始までにかかる費用 | 0円 | 法定費用+資本金【法定費用】株式会社:約25万円~合同会社:約10万円~ |
| 3.税金 | 所得税個人住民税個人事業税消費税 所得税は所得が多くなるほど税率が高くなり、控除が少なくなる | 法人税法人住民税法人事業税消費税 など 法人税は所得税よりも税率の推移が穏やか |
| 4.社会保険負担の有無(従業員分含む) | なし(従業員5人未満の場合) | あり |
| 5.事業維持にかかる費用(税金以外) | なし | 社会保険料の企業負担あり |
| 6.経費の範囲 | 事業にかかる費用は基本的に計上できる 自分への給与や生命保険料は経費にできない(後述) | 個人事業主よりも経費の範囲が広い 個人事業主では経費にできない以下のものも経費計上できる可能性がある 社宅の家賃出張時の日当生命保険料(法人契約)役員報酬(自分・家族) |
| 7.社会的信頼度 | 法人に比べて低い事業を行ううえでの支障は特にない | 高い新規の契約や融資にも有利 |
| 8.資金調達 | 小規模な資金調達方法がほとんど | 大規模な方法での資金調達が可能 |
| 9.事業の廃止 | 廃業届を税務署へ提出 | 法務局や税務署などへの解散登記・公告などが必要(少なくとも8万円程度はかかる) |
| 10.事業承継のしやすさ | しにくい | しやすい |
| 11.赤字の繰越 | 3年(青色申告の場合) | 10年 |
| 12.責任範囲 | 無限責任 | 有限責任 |
| 13.会計・経理 | 個人の確定申告 | 法人決算書・申告(税理士が必要になることが多い) |
引用元:個人事業主と法人の違いは?13項目で比較した特徴とメリット・デメリットや法人化を選択するポイント
それぞれでかなり違いがあることがお分かりになるでしょう。特に法人登記でメリットが大きいのが社会的な信用が高まることです。その結果、取引でも有利になるし、金融機関の融資も受けやすくなります。
会社登記の必要な基本書類と追加書類の種類
画像引用元:写真AC
会社登記をするに当たって必要な基本書類があるほか、さらに追加書類を準備しなければいけないケースもあります。その内容を確認してみましょう。
基本書類一覧(定款、印鑑証明書、払込証明書など)
会社登記に当たって必要な基本書類一覧を示しましょう。
- 設立登記申請書
- 登録免許税分の収入印紙
- 定款
- 発起人の印鑑証明書
- 資本金の払い込みを証明する書面
- 印鑑届書
- 登記用紙と同一の用紙など
事業形態に応じて追加される書類とは?
事業形態に応じて必要になる追加書類もあります。
▶株式会社の場合
- 発起人の同意書
- 設立時代表取締役を選定したことを証する書面
- 設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書
- 設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類
- 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書
- 委任状など
▶合同会社の場合
- 登記事項証明書
- 職務執行者の選任に関する書面
- 職務執行者の就任承諾書
- 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書
- 委任状など
記載内容に注意が必要な書類:定款や商号決定時の注意点
会社登記で提出する書類によっては、記載内容に注意すべきものがいくつかあります。
例を挙げてみると、まず定款です。定款には3種類の記載事項がありますが、このうち絶対に含めなければいけないのが絶対的記載事項です。絶対的記載事項を記載しないと、会社が成立しません。
絶対的記載事項とは、次のようなものです。
- 事業の目的
- 商号
- 本社所在地
- 資本金額
- 発起人の氏名と住所など
次に商号決定時は次のようなことに注意しましょう。
- 他社の商号をマネしない
- 必ず会社の種類を記載する
- 公序良俗に違反しない商号にする
- 不正競争防止法に触れない商号にする
- 同一住所で同一商号は使えない
- 法人形態、業種に合致させる
- 使用不可の文字は使わない
登記手続きでかかる諸費用と節約方法
画像引用元:写真AC
登記手続きをする際には費用がかかります。その費用の内訳と費用の節約方法を説明しましょう。
登記手続きにかかる基本費用(登録免許税・公証費用など)
登記手続きにかかる基本費用は次のようなものです。
- 登録免許税
- 公証費用など
登録免許税の額は、設立する会社の種類によって変わってきます。以下の表で確認してみましょう。
| 会社の種類 | 登録免許税の額 |
| 株式会社 | 資本金×0.7%、もしくは15万円未満のときは、申請件数1件につき15万円 |
| 合名会社または合資会社 | 申請件数1件につき6万円 |
| 合同会社 | 資本金×0.7%、もしくは6万円未満の場合は、申請件数1件につき6万円 |
次は、公証費用。法人登記における公証費用とは、定款の認証手数料のことです。定款の認証手数料は資本金の額によって変わってきます。
| 資本金額 | 定款の認証手数料 |
| 100万円未満 | 3万円 |
| 100万円以上300万円未満 | 4万円 |
| 300万円以上 | 5万円 |
電子定款利用による印紙税の節約効果
定款認証を受ける際に書面で作成すると、課税対象になり、印紙税4万円が発生します。
一方、電子定款は課税文書ではないので、印紙税を支払う必要はありません。つまり、多少の節約ができるということです。
オンライン手続きを利用するメリットとデメリット
法人登記をオンラインで手続きすることもできますが、そのメリットとデメリットを説明しましょう。
▶オンライン申請のメリット
法人登記申請をオンラインで行うメリットは次のようなことです。
- 法務局に出向く必要がなくなる
- 登記申請から完了まで原則24時間で完了する
- 申請状況をリアルタイムで確認できる
法人登記をオンラインで申請すれば、法務局に出向いての手続きが不要になります。
「時間が取れない」「法務局が遠い」などの場合は、オンライン申請は非常に便利です。
これで時間も交通費も節約できるでしょうし、何時でも申請ができるので、忙しい方でも対応できるでしょう。
通常では法人登記申請をしてから、手続きが完了するまで1週間程度かかるものですが、オンライン申請なら24時間以内に完了することになります。これで会社設立に向けてのスケジュール調整もしやすくなります。
手続き完了までが早いのが法人登記のオンライン申請ですが、それだけでなく申請の進捗状況をリアルタイムで確認することが可能です。「登記・供託オンライン申請システム」により、受付が確かに成されたのか、手続きがどこまで進捗しているかなどを確かめられます。これで安心して、手続き完了を待てるでしょう。
▶オンライン申請のデメリット
法人登記をオンライン申請するデメリットも確認しておきましょう。
- 準備と実施で手こずることがある
- 分からない点をすぐに質問できない
- 不備があると、却下されてしまう
オンラインで法人登記をするための準備がありますが、まずここをクリアする必要があります。「登記・供託オンライン申請システム」のダウンロードやマニュアルの閲覧などです。マニュアルをしっかり読んでおかないと、手続きを進められません。
電子署名ソフトやICカードリーダライタなども準備する必要があります。
実施に当たって、電子証明書・電子署名・電子納付などの手続きも生じますが、電子データの扱いに慣れていないと、少し面倒です。
電子申請で法人登記をする方法は便利ではあるのですが、途中で分からないことが出てくる場合もあります。その際はマニュアルなどを参考に自分で対処法を確認しないといけません。担当者にすぐに質問して、答えてもらうというわけには行かないのです。窓口申請ならその場で質問ができますが、ここはオンライン申請のデメリットでしょう。
オンラインで法人登記申請をして、不備が見つかり修正が必要と言うことになると、その時点で却下されてしまいます。軽微な不備であれば、修正し直して送信ということも可能ではありますが、それでも期限内に送信しないといけません。
修正箇所が生じないように申請するのが理想ではあるものの、人によっては難しく感じることもあるでしょうから、その場合は窓口申請がおすすめです。
オンライン登記手続きと電子定款の活用法
画像引用元:写真AC
オンライン登記手続きのメリット・デメリットを紹介しましたが、電子定款と合わせて上手に活用すれば、これほど便利なものはありません。そこでその活用法を説明しましょう。
電子定款とは?その仕組みとメリット
電子定款は会社の基本情報やルールを電子ファイル(PDF)でまとめたものです。電子定款を作成するに当たって準備は必要ですが、書面による定款よりも様々なメリットがあります。
- 電子定款なら、早く作成できる
- 印紙税が不要
- 印刷する必要がない
オンライン登記手続きの流れと注意点
法人登記をオンラインで行う流れを説明しましょう。
- 事前準備:申請者情報の登録や「登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと」内の「申請用総合ソフト」のダウンロード
- 申請者情報の作成:登記の目的に合った申請様式を選び、示された項目ごとに入力していく
- 添付書類をオンラインで提出する:事前に電子証明を付与しておく。電子データ化できない書類は、窓口に持参するか郵送で送る
- 申請データを送信する:申請書情報と添付書面情報に電子証明を付与し、送信する
- 「処理状況表示」画面から、手続き進捗状況を確認する
- 登録免許税・登記手数料の納付をする:「電子納付」か「領収書または印紙納付」かのいずれか
- 補正の通知があった場合、その指示に従って、再提出・修正・追加情報の添付などを行う
続いて、オンライン登記手続きの注意点です。
- 商業登記電子証明書が必要
- 24時間以内に手続きを完了するためには条件がある
オンラインで法人登記の手続きをする場合に必要になるのが商業登録電子証明書です。これがないと電子証明の付与ができませんから、電子申請手続きが頓挫してしまいます。
そこで請求方法を説明しておくと、法人登記の際に使う申請用総合ソフトからできます。
オンラインによる法人登記手続きは原則24時間で完了するのですが、その条件を確認しておきましょう。
- 役員などが5人以内である
- 添付書面情報(定款、発起人の同意書、就任承諾書など)が全部PDFファイルで作成されて、送信されている
- 登録免許税の納付を電子納付で行っている
- 補正箇所がない
以上の条件をすべてクリアできると、オンラインによる法人登記手続きが申請後24時間以内に完了します。
オンライン登記を利用する際の準備事項
オンラインによる法人登記をする際には準備しておかないといけない事項があるので、確認してみましょう。すでに少し説明してありますが、もう少し詳しく解説します。
まず、法務省の「登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと」から、申請者情報の登録をしてください。これは必須事項です。
登録画面から必要事項を入力すると、申請者ID・パスワードが発行されます。申請者ID・パスワードは後ほどログイン時に使いますから、保管しておきましょう。
後は、「登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと」内の「申請用総合ソフト」のダウンロードです。
なお、ブラウザシステム版の「かんたん証明書請求」「供託かんたん申請」もありますが、これでは法人登記はできません。
登記手続きのサポートを行う専門家と相談先の選び方
画像引用元:写真AC
法人登記を自分で行うこともできますが、手続きが面倒になることもあります。そのようなときは、サポートをしてくれる専門家や相談先に当たるのがおすすめです。
では、どのような専門家や相談先を選べばいいのかということになるでしょうから、選び方のポイントを解説しましょう。
登記手続きでサポートを受けられる専門家とその役割
会社の設立に関する相談ができる士業の専門家はいろいろありますが、法人登記のサポートは司法書士の独占業務です。司法書士は次のような登記に関する業務ができます。
- 定款などの書類作成
- 登記申請書の作成
- 定款認証
- 設立登記申請
専門家への依頼メリットと費用の目安
司法書士に法人登記申請を依頼するメリットは次のようなことです。
- 登記申請がスムーズに進む
- 手続きのミスが起きにくくなる(補正が必要になることはあまりない)
- 本業に専念できる
司法書士に法人登記手続きを依頼する費用目安は単発契約か顧問契約かによって異なります。
単発契約の場合の費用目安は、1回分が5~20万円程度です。顧問契約となると、月額費用を支払うことになりますが、これは各司法書士によって変わることです。依頼前に確認しておきましょう。
無料相談を活用する方法と公的機関のサポート
法人登記の無料相談は、法務局や商工会議所、商工会、日本政策金融公庫、東京司法書士会などで実施されています。司法書士事務所でも無料相談を受け付けている場合もあります。
ここでは、法務局と東京司法書士会の無料相談をご案内しましょう。
法務局では、基本的な申請内容の相談ができます。予約制になっていて、予約は電話や法務局のWebサイト「法務局手続案内予約サービス」からできます。1回の相談時間は20分ほどです。
東京司法書士会の場合、WEB・面談・電話・出張などで登記の無料相談ができます。ただ、WEBや電話による相談では内容に限りがあるので、詳しい相談をしたい場合は、面談相談を利用してください。
まとめ
今回は、会社設立時に必要になる法人登記について詳しい説明をしました。
法人登記は自分で行うこともできます。しかし、手続きが面倒になりやすいのと、補正などの不備が生じることもあります。そうなると、後でさらに作業が増えて、タイヘンです。
そのようなことが煩わしく感じるのなら、専門家に相談するのがおすすめです。相談だけなら無料というケースも多いです。依頼する場合は費用がかかりますが、費用がかかっても手続きがスムーズに進むので、依頼するメリットは大きいです。