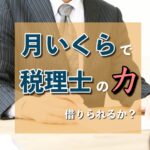COLUMN経営コラム

COLUMN経営コラム

【簡単解説】年末調整の対象期間|12月分1月支払の給与は?
投稿日:2022.08.08
更新日:2023.04.11
税務
業務多忙の中、初めて年末調整業務に当たる経営者や担当者は大変な思いをしてらっしゃるかと思います。
どれだけ多忙でも、ミスが出て後から面倒な処理がついてくるのは避けたいところです。
この記事では、年末調整で取り扱う給与の対象期間はいつからいつまでなのか、初めて業務に当たられることを想定してわかりやすく解説しています。
「1月支払予定の12月分給与はどう取り扱うのか?」にもお答えします。円滑に年末調整業務を進めていきましょう。
▼ この記事の内容
年末調整の対象期間は1月1日〜12月31日

年末調整は、概算で給与天引き(源泉徴収)した所得税額を確定させ、12月分か翌年1月分の給与で差額を還付・追加徴収する手続きです。
対象期間としては、その年の1月1日から12月31日の間に支払った給与を取り扱います。
こちらの記事をご覧ください。
年末調整は税理士に依頼するべき? | 料金の相場はどのくらいか
「12月分1月支払」の給与は対象期間に含む?

対象期間が1月1日〜12月31日だとわかったところで、「翌年1月支払予定の今年の12月分給与は、対象期間に含めていいのか?」という疑問が生じます。
今月分の給与を翌月に支払う企業が一般的であるためです。
「12月分1月支払」の給与は対象期間に含まない
結論としては、翌年1月に支払う予定の今年の12月分給与は、年末調整の対象期間には含みません。
今年の1月に支払った昨年12月分の給与は、対象期間に含まれることになります。
何月分かではなく、契約で定められた給与支給日が重要
該当の給与が対象期間に含まれるかは「契約で定められた支給日や慣習的な支給日」で判断します。
まず、対象期間に含まれるのは、国税庁がいう「その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与」です。
この「支払うことが確定」した時点とは、就業規則や雇用契約で定められた給与支給日を指しているのです。
例えば今月分の給与を翌月の25日に支払っている企業では、翌月の25日が支払い確定日となります。
また、給与支給日が雇用契約に定めたものではなく、慣習的に一定の日に支給している場合でも同様に取り扱って差し支えありません。
給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。・・・・・・契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
支給日が定まっていない給与の場合
支給日が定まっていない給与については、実際に給与を支給した日をもって「支払うことが確定」します。
未払い給与は対象期間に含まれる?

では、なんらかの事情で支払いが遅くなっている給与を今年支払った場合、対象期間に含まれるのでしょうか?
先程お伝えしましたとおり、判断基準は「契約で定められた支給日や慣習的な支給日」が対象期間に含まれるかどうかです。
ですから、例え実際に未払い給与を支払ったのが今年だとしても、本来の支給日が去年であれば年末調整の対象期間から外れることになります。
例えば、前年の10月分11月25日支払いの給与が未払いなら、前年11月25日が本来の支給日です。ですから、今年の1月1日〜12月31に含まれず対象期間外となります。
【よくあるケース】こんな場合は対象期間に含まれる?

対象期間に含まれるかの判断がしづらいケースは、他にもあります。
年の途中で退職した従業員の給与
基本的に、年の途中で退職した従業員については年末調整を行いません。
転職先で年末調整を受けるか、従業員自ら確定申告してもらうことになります。
ただし、例外もありますので以下に注意してください。
【途中退職でも年末調整が必要な場合】
- 12月に支払われる給与等の支払を受けた後の退職
- 死亡退職
- 心身の不調で退職、再就職しないことが明確である
- 今年の給与総額が103万円以下のパートタイマーが退職
年の途中に転職してきた従業員の前職分給与
今年の途中に従業員が転職してきた場合、1月1日〜12月31日の間に前職で支払われた給与は対象期間に含まれます。
従業員が前職で受け取った給与も含めて年末調整しましょう(前職の源泉徴収票が必要)。
海外赴任する、あるいは帰国した従業員の給与
従業員が海外赴任する場合や年の途中で海外赴任から帰国した場合の、年末調整対象期間に該当する給与は以下のとおりです。
- 年の途中で海外赴任・・・1月1日から出国するまで
- 年の途中で帰国・・・帰国した日から12月31日まで
- 年間を通して海外赴任・・・年末調整の必要なし
参照:海外に転勤した人の源泉徴収|国税庁HP
参照:海外勤務と所得税額の精算|国税庁HP
さて、ここまでは年末調整で取り扱う給与の対象期間について解説してきました。
次の見出しで、年末調整書類の提出期間・修正期間を簡単にお伝えし、この記事を終わりにします。
税務署に提出すべき書類については、こちらの記事をお役立てください。
【わかる】年末調整で税務署に提出する書類|ミスなく業務を完了する
年末調整書類の提出期間は?

年末調整書類は、翌年1月31日までに税務署に提出します。
ただし、年末調整で確定した所得税は、同1月10日までに管轄の税務署に納める必要があります。
従業員から書類を提出してもらった後、計算する時間も必要ですから、12月上旬までには従業員から書類を提出してもらえるようにしましょう。
翌年1月31日の期限を大きく過ぎた場合は、従業員が自分で確定申告しなければなりません。
数日遅れた程度なら待ってもらえる場合もありますが…、早めに段取りをして期限に間に合わせるのが確実です。
前職の源泉徴収票が間に合わない場合の対応を、詳しく解説いたしました。
年末調整の修正が可能な期間は?
従業員が提出した書類に誤りがあった場合、従業員に対して源泉徴収票を発行するまでの間は修正が可能です。
最長で翌年1月31日(給与支払報告書の提出期限)までが修正可能な期間となります。
この記事のまとめ
この記事では、年末調整で取り扱う給与の対象期間について解説してまいりました。
- 年末調整では、その年の1月1日から12月31日の間に支払った給与を取り扱う。
- 翌年1月支払予定の今年の12月分給与は、今年の年末調整の対象外。
- 該当の給与が対象期間に含まれるかは「契約で定められた支給日や慣習的な支給日」で判断する。
当記事をご活用いただき、トラブルなく年末調整業務を終えていただけましたら幸いです。
また、来年以降の年末調整業務をより効率化されたい場合は、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら