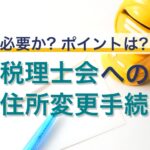COLUMN経営コラム

COLUMN経営コラム

税理士変更の理由と引継ぎ手続きの流れ|最適なタイミングと注意点
投稿日:2022.11.25
更新日:2024.10.11
税務経営

税理士を変更したいと考える主な理由には、業務の進行に支障をきたす対応の遅れや、高額な料金、コミュニケーション不足などが挙げられます。税理士の変更は、企業経営においてしばしば重要な決断となりますが、変更に最適なタイミングや具体的な手続きについては不明な部分が多いのではないでしょうか。
本記事では、税理士変更の一般的な理由から、理想的な変更のタイミングや手続きに至るまで、具体的なステップを詳しく解説します。税理士選びの際の注意点や、変更後のフォローアップ方法についても触れながら、より良い税理士と共に成長するための情報を提供します。
▼ この記事の内容
税理士変更の一般的な理由
税理士を変更したいと考えるきっかけは、さまざまな理由が存在します。まず、対応が遅いという問題がしばしば挙げられます。特に税務業務は期日厳守が重要であり、提出期限が迫る中での遅延は、企業にとって致命的なリスクを伴います。
また、費用が高額すぎると感じる場合も、税理士変更を検討する要因となります。契約時には適正だと思われた料金も、事業の規模が変わる中で割高に感じられることがあります。加えて、コミュニケーション不足も深刻な問題です。
特に、経営者と税理士との間でスムーズな情報共有が行われない場合、重要な決断に影響を及ぼす可能性があるため、税理士変更を検討する企業が多いのです。
【徹底解説】税理士を変える”全タイミング”
税理士を変更するタイミングは非常に重要です。どの時期に変更するかによって、その後の業務がスムーズに進むかどうかが決まるため、慎重に判断する必要があります。以下で詳しく説明していきます。
【ベストタイミング】法人税申告書の提出直後
法人税申告書を提出した直後は、税理士を変更するための理想的なタイミングです。法人税の申告を済ませた後であれば、税理士に依頼する大きな業務は一段落しています。
具体的には、決算月が3月であれば、3月31日の2ヶ月後、法人税申告期限の5月31日以降であれば、次の事業年度に向けた新しい税理士との契約がスムーズに進行します。税理士は月次業務などを経て、年度末に法人の財務状況をまとめ決算書を作成しますが、その決算書に基づいて最後に作成されるのが「法人税申告書」です。法人税申告で税務署に年度の納税額を伝えてしまえば、現在の事務所にお願いする大きな業務は、もうありません。
この時期であれば、旧税理士からの引き継ぎ業務も比較的少なく、新しい税理士が業務を円滑に開始できるのです。
【変更の工夫】旧税理士と新税理士を一時的に同時に雇う
一時的に旧税理士と新税理士を同時に雇うという方法もあります。新年度が始まるタイミングで新しい税理士が業務を開始しつつ、旧税理士は決算業務を完了させることで、引き継ぎに伴うリスクを最小限に抑えることが可能です。この方法は、特に現在の税理士に対する不満が大きく、変更を急ぐ場合に有効です。
ただし、デメリットとしては、数ヶ月間の間、二人の税理士に支払う報酬が発生する点があります。それでも、円滑な引き継ぎを優先したい場合、この方法を検討する価値はあります。
【税務調査がある場合】修正申告が終わった後がベスト
税務調査が行われる可能性がある場合、修正申告が完了したタイミングで税理士を変更するのが最も賢明です。税務調査の対象となった場合、その申告に誤りや漏れがあると、税務署からの指摘を受け修正申告を行うことになります。修正申告は、もともと申告を担当していた税理士が処理するのがスムーズであり、その後で新しい税理士が引き継ぐ方がリスクを減らせます。
新しい税理士が税務調査対応・修正申告する際に必要な「税務代理権限証書」の手続きも、税務調査が決まってからの税理士変更では間に合わないリスクが高くなります。また、税理士を変更したからといって、税務署の調査が中止されることはありません。重要なのは、申告を適切に行い、その後の業務を新税理士に任せることです。
【その他】決算3ヶ月前〜法人税申告を外せば変更可能
税理士の変更を検討している時期が、法人税申告の期限から遠い場合もあるかと思います。そのような場合、決算3ヶ月前から法人税申告の期間を避けることで、比較的スムーズに税理士の変更を進めることができます。決算3ヶ月前から法人税申告までの期間は、税理士の変更を避けたほうが良い時期です。この期間は、新しい税理士が引き継ぎに十分な時間を確保できない可能性があるため、決算や申告に影響を与えるリスクが高くなります。
税理士の多くは、決算3ヶ月前から準備を始めており、この期間に変更を強行するのは避けるべきです。もし変更が必要な場合は、繁忙期を外した時期を選ぶと、税理士側も余裕を持って対応してくれるでしょう。
決算3ヶ月前〜法人税申告にどうしても税理士を変えたい場合
決算3ヶ月前〜法人税申告にどうしても税理士を変更したい場合でも、条件次第では可能です。例えば、会社の規模が小さく、引き継ぎ業務が少ない場合や、税理士事務所が閑散期である場合には、対応してもらえる可能性が高まります。特に、6月から10月は多くの税理士事務所が比較的業務が少ない時期です。この期間にタイミングが合えば、税理士変更の可能性が広がるでしょう。
また、積極的に仕事を引き受けるスタンスの事務所である場合や、若手税理士が中心の事務所である場合も、税理士変更を可能とする要素の一つとなるでしょう。反対に、会社の売上規模が5億円超など、引き継ぎ量が膨大となることが予想される場合や、税理士事務所の繁忙期である11月から5月の時期である場合、税理士の変更を引き受けてもらうことは厳しいでしょう。
税理士変更の具体的な手順とスケジュール|『いつ』『何を』すれば良いのか?
ここでは、税理士変更の手順とスケジュールについて説明します。税理士変更を検討している際には、事前にしっかりとした計画を立てることが重要です。これにより、スムーズな引き継ぎが実現できます。具体的に「いつ」「何を」すれば良いのかを、以下で詳しく説明していきます。
手順①契約内容を確認し[税理士を変えるタイミング]を決める
税理士を変更する前に、まずは現在の税理士との契約内容をしっかりと確認することが必要です。契約解除の条件や手続きについて、具体的に理解しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。契約の解除条件には、解約通知の期限や方法、また解約に伴う手数料の有無などが含まれます。
特に注意が必要なのは、契約解除が決算期や税務調査の直前に行われると、業務に支障が出る可能性があるため、事前にスケジュールを調整しておくことが望ましいです。
手順②早めに新しい税理士を見つける
税理士を変更する際には、新しい税理士を早めに見つけることが非常に重要です。現在の税理士との契約が終了した後に、税理士不在の期間が生じると、業務の継続性が損なわれる恐れがあります。このため、
特に決算や申告が近い場合、早期に新しい税理士を見つけておく必要があります。新しい税理士との契約のタイミングや必要な書類を確認し、スムーズな引き継ぎを実現することが求められます。
手順③期間内に現在の税理士に断りを入れる
現在の税理士に変更の旨を伝える際は、非常に気を使う場面です。しかし、円満に変更を進めるためには、正しい方法で断りを入れることが重要です。まず、感謝の意を述べることで、相手に対する配慮を示します。
また、契約解除の理由を明確にし、次のステップを伝えることで、相手に理解してもらいやすくなります。その後、書面での正式な通知を行うことが望ましく、これによってトラブルを未然に防ぐことができます。
さらに、解約通知を行う際には、協力を引き出すための対応も必要です。具体的には、引き継ぎ業務に関するお願いをすることで、今後のスムーズな業務継続に役立ちます。
手順④早めに書類を返却してもらう
税理士変更に伴い以前の税理士から書類を返却してもらう必要がある場合、まず書面での依頼を行うことが重要であり、依頼書には感謝の意を表しつつ、契約終了のために必要な書類を返却してもらいたい旨を明記し、優先的に返却してもらいたい書類リストを作成して具体的な期限を設定し、書類の返却方法や連絡先を記載することが望ましいです。
返却してもらうべき書類には、下記の書類が挙げられます。
- 総勘定元帳
- 決算書
- 会社の定款
- 登記簿謄本
- 法定調書
- 償却資産申告書
- 過去の税務署への提出書類
- 年末調整関係書類
- 期中の会計データなど
その中でも優先度の高い書類としては、総勘定元帳や決算書、法定調書・償却資産申告書、期中の会計データなどがあり、これらは業務のスムーズな引き継ぎに不可欠であるため、契約終了日から2週間以内に返却されるよう依頼することが望ましいです。
万が一書類が返却されない場合には、再度の連絡を行い、書類の重要性を強調し、契約書に基づいた依頼を行い、それでも解決しない場合は法的手段を検討する必要があります。
最後に、データ形式については、受け取りたいデータの形式(ExcelやPDFなど)や、書類の郵送方法(書留や宅急便)を明確にし、特に個人情報や機密情報が含まれる場合はセキュリティ対策を施してデータを送信してもらうよう依頼することが大切です。
手順⑤新しい税理士が引き継ぐ
必要書類の返却を受けた後は、新しい税理士が法人の経営状況や事業内容を正確に把握し、業務を開始します。この段階で、新しい税理士とのコミュニケーションが重要になります。経営状況や事業内容について十分な情報を提供することで、新しい税理士が効果的なサポートを行えるようになります。また、新たな契約の内容や料金体系についても明確にし、今後の業務運営における信頼関係を築くことが成功の鍵となります。
税理士変更にかかる時間と費用
ここでは、税理士を変更する際にかかる時間と費用について具体的に説明していきます。
まず、引き継ぎにかかる時間ですが、通常は数週間から数ヶ月の間で変動します。この期間は、現行の税理士と新しい税理士との間でのコミュニケーションや必要書類の準備状況、そして税務業務の繁忙度によって影響を受けます。
特に、年度末や決算期に当たる場合は、引き継ぎがスムーズに進まないことも考えられます。次に、税理士変更時のコストについてです。新しい税理士を雇う際には、初回の相談料や契約料が発生することが一般的です。
さらに、引き継ぎに際して必要な書類の整備やデータ移行にかかる作業費用も考慮する必要があります。
これらを合計すると、税理士変更にかかるトータルコストは数万円から数十万円に達することもあります。したがって、変更を検討する際には、時間と費用を十分に計算し、無理のないプランを立てることが重要です。
【デメリット】スムーズな税理士変更に向けて注意すべきこと
税理士を変更する際には、タイミングによって業務に支障が出る可能性があることを理解しておくべきです。例えば、繁忙期に変更を行うと、業務が滞りやすくなります。そのため、事前に次の税理士と引き継ぎスケジュールを確認し、空白期間ができないように調整を行うことが必要です。また、業務が滞らないように、現在の税理士に残務処理を依頼する際には、明確な期限を設定することが重要です。
その他のデメリット・リスクと対策
会社への理解や肌感覚は、新しい税理士には引き継げないという点も重要なリスクです。これを防ぐためには、新しい税理士との初期のコミュニケーションを密にし、会社の業務内容や経営方針を丁寧に説明することが求められます。経理担当者がいる場合には、その人からも詳細な引き継ぎをサポートしてもらうことで、よりスムーズな移行が実現します。
また、引き継ぎがスムーズに行われない可能性も考慮しなければなりません。このリスクに対処するためには、早めに返却すべき書類をリストアップし、返却期限をしっかりと設定して現在の税理士に依頼することが重要です。さらに、次の税理士に対しても、使用している会計ソフトやデータ形式を確認し、スムーズな移行ができるように準備しておくことが大切です。
加えて、新しい税理士にも不満を抱く可能性があるため、選び方には慎重さが求められます。税理士選びの際には、事前に業務内容や期待するサービスをしっかりと話し合い、相性を見極めることが不可欠です。契約前にお試し期間を設けたり、過去の実績やクライアントの声を参考にしたりすることで、より信頼できる税理士を見つけやすくなります。
新しい税理士の選び方
新しい税理士を選ぶ際には、いくつかの具体的な基準を設けることが重要です。まずは、依頼内容に応じた専門分野を確認しましょう。例えば、法人税や相続税、消費税など、自社の業務に特化した知識を持つ税理士を選ぶことで、的確なアドバイスが受けられます。
次に、報酬額の相場を把握し、他の税理士と比較することが求められます。透明性のある料金体系を持つ税理士を選ぶことで、予算の管理も容易になります。選定時には口コミや評判の確認も欠かせません。インターネット上のレビューや知人からの推薦を参考にすることで、信頼性の高い税理士を見つける手助けになります。
また、直接面談を行い、相性やコミュニケーションの取りやすさを確認することも重要です。これにより、長期的に良好な関係を築くための基盤ができます。
引き継ぎ後のフォローアップ
税理士変更後には、新しい税理士との信頼関係を構築するためのフォローアップが必要です。具体的には、定期的なミーティングを設け、業務の進捗状況や課題を共有することで、信頼関係が深まります。また、税理士変更後に発生する可能性がある課題についても事前に把握し、適切な対策を講じることが大切です。新しい税理士が自社の業務内容を理解し、効果的なアドバイスをもらうためには、初期段階でのコミュニケーションが鍵となります。
まとめ
税理士の変更は、企業にとって避けて通れない重要なプロセスです。変更に伴うリスクを最小限に抑えつつ、スムーズな引き継ぎを実現するためには、正確なタイミングを見極め、計画的に行動することが不可欠です。特に、契約内容の確認、新しい税理士の選定、旧税理士との円満な関係の構築は、成功の鍵となります。
さらに、変更後のフォローアップを通じて新しい税理士との信頼関係を深め、自社の成長に寄与するアドバイスを受けるための基盤を築くことが重要です。
本記事で述べた内容を参考に、より良い税理士との出会いと、持続的なビジネスの発展を目指してください。FLAGSグループは、名古屋市で50年以上にわたり、中小企業の継続的な発展を支援しています。クラウド会計ソフトの導入や、公的制度支援やM&A支援など幅広いサービスも提供しており、変化の激しい経済環境において、顧客のニーズに迅速に対応し、総合的なサポートを続けています。税理士の変更に関するご相談はぜひFLAGSグループにお任せください。