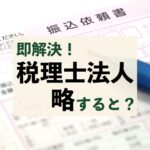COLUMN経営コラム

COLUMN経営コラム

クラウド会計を使うみなさん必読! 税理士・会計事務所の選び方とは?
投稿日:2022.08.30
更新日:2024.07.25
経理クラウド
クラウド会計ソフトの登場により、自社で会計・経理を賄う会社が増えています。しかしながら、このような時代だからこそ「税理士のサポート」が必要不可欠です。
この記事では、「クラウド会計×税理士」をテーマとし、両者を導入すべき理由や会計事務所の選び方について、解説します。この記事を最後までお読みいただければ、手間な会計・経理の不満がなくなり、みなさん自身が事業展開に集中することができる方法を選べることでしょう。クラウド会計ソフトを導入すると、会計・経理業務が効率化し、確定申告もしやすくなるので、「もう税理士はいらない」と思いたくもなるでしょう。
▼ この記事の内容
クラウド会計ソフトを導入したら税理士は不要なのか
実際のところどうなのか、考えてみましょう。
効率化はできても、正しい決算書・申告書を自動で作成できるわけではない
クラウド会計ソフトを使用すれば、会計・経理業務が効率化するのは確かです。しかし、決算書や申告書の作成を自動で行ってくれるわけではありません。決算書や申告書は自分で作成しなければいけないのですが、ここで間違いやおかしなことが生じやすいのです。クラウド会計ソフトがあるから、正しい決算書や申告書が作成できると思っていると、当てが外れることがあります。正しい書類を作成し、確認してもらうためには税理士に依頼して行ってもらうのが一番です。
税理士に確定申告を依頼する場合と自分で行う場合の違い(個人事業主)
個人事業主が確定申告をする場合、税理士に依頼する場合と自分で行う場合の違いがあります。まず税理士に依頼すると、次のようなメリットがあります。
- 税務調査の可能性が減る
- 税務調査時は立会いを依頼できる場合もある
- 税法上の特例等を提案され、節税できる場合もある
税理士に確定申告を依頼すると、決算書や確定申告書の提出前にチェックしてくれるので、間違いのない書類作成ができ、税務調査が入る可能性が減ります。仮に税務調査があっても、税理士に立会いを依頼できる場合もあります。また、具体的な節税対策を教えてもらえるのもメリットです。自分で確定申告をする場合は、税理士依頼料がかからないのがメリット。ただ、手間がかかりやすい、税金の額を間違えることがあり、税務調査が入ることがあるなどのデメリットがあります。
法人は税理士顧問を付けるのは必須に近い
個人事業主の場合、会計ソフトを使って自分で確定申告の作成ができないわけではありません。しかし、法人ともなると、経理・会計業務も増え、複雑化。税金申告も一段と難解になります。そのような業務を自社内のスタッフだけで対応できる場合もありますが、専門の税理士を付けていた方が誤りのない作業ができます。
何も不安にならずに依頼できることが顧問税理士を雇うメリットです。法人が顧問弁護士を付けるメリットをもう少し詳しく解説しましょう。
法人の決算・税務申告は個人事業主よりも複雑です。1年間の帳簿の漏れやミスの確認、期末に残った在庫数の確認などの作業も生じ、専門的な知識も必要になります。日々の記帳や帳簿の整理、決算に必要な書類の作成、申告や納税などの作業にも時間や手間がかかります。それらの業務を顧問税理士無しにやっていくのは大変なことです。もし誤りや手違いなどがあれば、税務調査の対象になり、罰則を受けることもあるでしょう。そうなると、取引先や金融機関からの信用を落としてしまう恐れもあります。
その点、顧問税理士に依頼すると、決算・税務作業を正確に行ってくれるので、間違いも生じにくくなり、税務調査が入る可能性が減ります。手続きもスムーズに進みやすくなり、余計な労力を使わなくて済むようになるでしょう。決算・税務処理を自社内で行っていると、リソースの確保も必要になってきますが、顧問税理士に依頼すれば、リソースも必要最小限で十分になります。経理業務に関するアドバイスを受けられるのも顧問税理士を付けるメリットです。
例えば、経費に関することです。クラウド会計ソフトでも経費の計上をしやすくはなっているのですが、法人ともなると経費の幅も項目も増え、扱いが難しくなることがあります。そのようなときに顧問税理士がいれば、的確なアドバイスを受けられるでしょう。顧問税理士には経営相談もできます。
顧問税理士は常日頃から法人の経営状況をチェックし、損益計算書や資金繰りの動きを見て、潜在的なリスクなども把握しています。そのため、法人の経営に関して相談もしやすいです。クラウド会計ソフトがいくら便利だとは言っても、経営相談はできないでしょう。
以上のような点から、法人にとっては顧問税理士を付けるのが必須とも言えます。
クラウド会計の導入は税理士顧問料を安くすることに繋がるのか
税理士を雇うことで会計や経理業務も効率化し、決算・税務処理も行いやすくなりますが、問題なのは顧問依頼料でしょう。自社内で業務を行うよりも、割高になると、依頼もしにくくなります。そこで考えたいのがクラウド会計の導入で税理士顧問料を安くすることに繋がるのか。答えを見てみましょう。
顧問料が安くなるかどうか考えるためには、どういった料金として顧問料を払っているのかを知ることが必要
税理士顧問料が安くなるかどうかを考える際に大事になるのが、どのような料金として顧問料を支払っているのか確認することです。そこで、税理士に毎月支払う顧問料の内容を見ておきましょう。
- 記帳代行料:請求書や領収書などの書類を税理士に共有し、会計ソフトへの入力を依頼する費用
- 監査・決算料:会計ソフトに入力されたデータのチェックや、税務上の判断、決算・申告を行う費用
税理士顧問料を安くするというのなら、この中の内容を減らすか、依頼時間を減らすかになるでしょう。
顧問料が安くなるケース
クラウド会計の導入で税理士顧問料が安くなるのは、次のようなケースです。
- 自社内で会計入力を済ます
- クラウド会計で記帳作業の手間を減らし、工数を削減する
- 税理士との面談の回数を減らす
それぞれのケースを解説します。
クラウド会計を導入し、自社内のスタッフだけで会計入力を済ますようになれば、記帳代行を税理士に依頼する必要がなくなるので、顧問料を安くできるでしょう。クラウド会計により自動仕訳になると、仮に税理士に記帳をお願いするにしても、手間も工数も減ります。そうなれば、顧問料も安くなります。
税理士とのやりとりで、紙資料の受け渡しを行っている場合、税理士の元を訪問したり、税理士の方で会社側に訪問してもらったりなどの機会も増えることになるでしょう。そのため、人的時間的なコストもかかりやすくなり、その分が顧問料に跳ね返ってきます。そこで行いたいのが会計関連のデータをクラウド会計で取得&自動仕訳すること。これで税理士との面談回数を減らすことができ、顧問料を下げられます。
顧問料が安くならないケース
クラウド会計を導入しても、税理士顧問料が安くならないことがあります。
次のようなケースです。
- 自動仕訳ルールが間違っていて、1年間そのまま会計処理が行われていた
- 記帳漏れや二重記帳が多かった
前者のケースでは、修正にかなりの時間と手間がかかり、税理士側の作業負担も増大するので、顧問料が安くなることはありません。後者のケースでは、原資資料のチェックをしなければならなくなり、やはり税理士の作業負担が増大。その結果、顧問料が安くなることはありません。クラウド会計の導入で、税理士顧問料が安くなるのはあくまでも次のような場合です。
クラウド会計を導入する⇒正確な自動仕訳を行う⇒税理士の作業や工数が削減される⇒記帳代行料が不要になる
上記の点をしっかり踏まえておいてください。
顧問料を安く抑えたい場合は対応範囲を確認する(トラブルの元となる)
税理士への顧問依頼料を安く抑えたい場合は、税理士の対応範囲を確認しておくことも大事です。顧問料を安くしている税理士の場合、対応範囲を拡大している可能性があります。
一般的な税理士の対応範囲は一人あたり20社程度ですが、顧問料が安い税理士では30~40社も扱うことがあるのです。これで安くなった顧問料分を補おうということなのでしょうが、対応範囲数が多い税理士には得てしてトラブルも生じやすいです」
対応範囲が多い税理士にありがちなトラブルは以下のようなことです・
- 対応が遅い
- 契約通りの回数打ち合わせが行われない
- 税務調査の立会いをしてくれない
- 試算表を毎月出してくれない(銀行融資に悪影響を及ぼす)
- 決算書のクオリティーが低い
- 経営相談ができない
上記のようなトラブルは避けたいでしょうから、ただ顧問料が安いという点だけではなく、サービスの質も確認しておきましょう。
決算間際に依頼をするのはNG
税理士顧問料を安く抑えたいのなら、決算間際の依頼はやめておきましょう。理由を説明します。
期首から遡って修正が必要になることがほとんどであり、1年分の記帳代行料を請求されるケースも
「クラウド会計で入力しておいたから、チェックだけしてください」ということで決算間際に税理士に依頼する人や会社がありますが、これは意外に面倒な作業なのです。期首から遡って修正が必要になることがほとんどのためです、そのため、1年分の記帳代行料を遡っての料金請求となることがあり、かえって顧問料が高くなることがあります。決算間際では税理士の作業も大変になり、苦労をかけることにもなるので、できるだけ前期の決算が終わったタイミングで依頼するようにしましょう。
新時代の最適解は「クラウド会計×税理士」
会計・経理のこれからの時代の最適解は、「クラウド会計×税理士」です。ここではその理由について、解説していきましょう。
理由①決算書・確定申告書の作成において税務調査が入るリスクを減らすことができる
理由の1つ目は、税務調査が入るリスクを減らせることです。
クラウド会計を使って自分で決算書や確定申告書を作成すると、入力ミスや計算違い、項目間違いなどがよく起きます。事業規模が小さい個人事業主の場合は、そのようなミスは減らせますが、売上が大きい個人事業主、法人では作業も複雑化し、ミスも起こりやすくなります。入力ミスがあるまま作成した書類をそのまま提出すると、税務調査が行われることもあるのです。
「クラウド会計×税理士」なら、そのような事態を防ぎやすいです。クラウド会計に対応した税理士なら、入力内容もチェックしてくれて、正しいかどうか見てくれます。そのため、正確な決算書や確定申告の作成ができるようになり、税務調査が入るリスクを減らせます。
理由②税理士から節税の提案を受けられる
理由の2つ目は、節税の提案を受けられることです。
クラウド会計を使って自分や自社で確定申告をしている場合、節税方法などは分かりにくいものです。いろいろなサイトを調べて節税対策することもあるかもしれませんが、その手間も面倒でしょう。また、本当に節税できるのか自信がないということもあるでしょう。
「クラウド会計×税理士」ということにしておくと、自分や自社では分からない節税方法の提案を受けることができます。個人事業主でも法人でも納める税金の額が大きくなれば、負担も増えます。その負担を少しでも減らそうと思えば、節税をすることが大事になりますが、その的確な方法を教えてくれるのが税理士です。
理由③:会計・経理でわからないことを的確に教えてもらえる
理由の3つ目は、会計・経理でわからないことを的確に税理士に教えてもらえるためです。
確かに、クラウド会計ソフトには、サービスの一環として「チャット」や「相談サポート」といったものがあります。しかし、これらのサービスは、
- チャットや電話ですぐに解決できないことがある
- 使用しているソフトやプランで利用できるサービスが異なる
- 個別具体的な内容に答えてくれないこともある
といった弱点も。個別で担当の税理士がついていれば、これらの問題はすべて解消します。この点は、会計ソフトの導入段階で考えておくべきポイントでしょう。
理由④:税理士からの個別のコンサルが受けられる
理由の4つ目は、税理士からの個別のコンサルが受けられるためです。
税金の世界は、「知っていないと損することが多い世界」と言えます。ある種“情報戦”とも言えるのですが、税理士がついていなければ、そのような情報は一切入ってきません。例えば、税理士のアンテナが高かったり、人脈が豊富だったり、であれば、みなさんにとって会計・経理以上のプラスの恩恵も受けることが可能です。税金の情報を制することで、みなさんの事業の発展にも影響を与えます。だからこそ、税理士をつけ、会計・経理を盤石にしていきましょう。
理由⑤:クラウド会計ソフトの困ったことも聞ける
理由の3つ目は、クラウド会計ソフトの困ったことも税理士に聞けるためです。
会計・経理の世界でも、“DX”が進んでいます。その最たる例が「クラウド会計ソフト」です。今では「クラウド会計ソフトが使える税理士」が標準化しつつあると言えるでしょう。そのような背景もあり、クラウド会計ソフトの操作や書類の作成方法等、クラウド会計ソフトの困ったことでも税理士に聞くことが可能です。この点は、みなさんにとっても安心できるポイントではないでしょうか?
クラウド会計に対応した会計事務所の正しい選び方とは?
以上までが「クラウド会計×税理士」が今の時代における最適解である理由でした。みなさんにも、クラウド会計ソフトと税理士の必要性は、ご理解いただけたのではないでしょうか?ここからは「クラウド会計に対応した会計事務所の正しい選び方」について、解説します。
選び方①:クラウド会計のことで税務相談ができるか
会計事務所の選び方の1つ目は、「クラウド会計のことで税務相談ができるか」です。
当然のように聞こえるかも知れませんが、「税理士がクラウド会計のことを理解しているかどうか」をちゃんと確認しておく必要があります。確かに、クラウド会計に対応した税理士が増えているのは事実です。しかし、まだまだ対応していない税理士も多いのも、これまた事実。だからこそ、税理士と契約を結ぶ前にしっかりと確認しておきましょう。クラウド会計のことで税務相談できなければ、本末転倒です。
選び方②:クラウド会計対応の税理士の顧問料は適切か
会計事務所の選び方の2つ目は、「クラウド会計対応の税理士の顧問料は適切か」です。
一般に、税理士の月額顧問料の相場は「2〜3万円」となっています。ただ、事業規模が大きければ、経営も交えた税務コンサルとなり、月額「10万円」を超えることも稀ではありません。もちろんこれは、税理士の依頼する内容によっても異なります。ただ、一方で相場よりも明らかに安い場合には、注意が必要です。「肝心な会計・経理の対応をしてもらえない」「税務相談の数も少ない」といったことも。そのため、税理士の顧問料は、事前にちゃんと調べておきましょう。
選び方③:オンラインですべて完結する会計事務所か
会計事務所の選び方の3つ目は、「オンラインですべて完結する会計事務所か」です。
「事業が忙しくて、会計事務所に行く時間がない…」みなさんも、思い当たることはないでしょうか?とくに事業がスタートしたばかりや好調な時にできる限り会計・経理で時間を取られたくはありませんよね?だからこそ、「オンラインで完結できるか」といった視点は大切です。今では、さまざまなオンラインツールがあります。ツールを活用すれば、移動やその準備までの余計な時間を節約することが可能です。だからこそ、「オンラインですべて完結する会計事務所かどうか」を契約前に確認しておきましょう。
選び方④クラウド会計各社の「税理士検索サイト」を活用
会計事務所の選び方の4つ目は、「クラウド会計各社の『税理士検索サイト』を活用する」ことです。
クラウド会計に対応した会計事務所を探すということなら、クラウド会計各社が用意している「税理士検索サイト」を活用するのがおすすめです。それぞれのサイトで、クラウド会計の知識や運用方法に詳しい税理士を紹介してくれます。ここでは、そのような「税理士検索サイト」を2つ紹介しましょう。
①クラウド会計freeeの税理士検索ページ
こちらのサイトでは、クラウド会計freeeの認定アドバイザー税理士を検索できます。
検索条件は、業種や業務内容、特徴、訪問可能地域、連絡手段など。
認定アドバイザーのランクは5つあり、5つ星アドバイザーが最高ランクです。
そうなると、星の数が多い税理士に依頼したくもなるでしょうが、星が多少少なくても、条件が合致すれば、質の高いアドバイスを期待できます。
掲載事務所数は2,000以上。豊富なデータを比較することができ、あなたの会社にぴったり合った税理士も選べます。
②マネーフォワードクラウドの税理士検索ページ
こちらはマネーフォワードクラウドに精通した税理士を検索できるサイトです。
マネーフォワードでは、独自にパートナー税理士のランク付けを行い、4つのランクを設けています。4つとは、ブロンズ/シルバー/ゴールド/プラチナのことです。右側へ行くほどランクが高くなります。
ランクが高いということは、それだけマネーフォワードクラウドに詳しいということです。
そのような税理士を探す場合、こだわり条件を指定しての検索も可能です。
こだわり条件は以下のようになっています。
- 区分
- 公認メンバーランク
- 都道府県
- 市区町村
- 得意業種
- 得意分野
- 特徴
- キーワード
この記事のまとめ
この記事では、「クラウド会計×税理士」をテーマとし、両者を導入すべき理由や導入するにあたって会計事務所の選び方について、解説しました。
この記事の内容をおさらいすると次の通りです。
クラウド会計ソフトで税理士が不要になるか
- クラウド会計があっても、正しい決算書・申告書を作成しなければいけない
- 確定申告を税理士に依頼するか自分で行うかの違い
- 法人の顧問税理士は必須
クラウド会計の導入で税理士顧問料が安くなるか
- 安くなる場合と安くならない場合がある
- 税理士の対応範囲を確認すること
- 決算間際に依頼しないこと
今の時代は「クラウド会計×税理士」の理由
- 会計・経理の基本的なことを聞ける
- 個別コンサルを受けられる
- クラウド会計ソフトのことも聞ける
クラウド会計に対応した会計事務所の正しい選び方
- クラウド会計で税務相談ができるか
- 税理士の顧問料は適切か
- オンラインですべて完結するか
冒頭でもお伝えの通り、時代は「クラウド会計×税理士」です。一方で、まだまだ新しい仕組みに対応しきれていない税理士が多いのも現実としてあります。ただ、みなさんが事業に集中できる環境を整えるためには、会計・経理のあり方も考えていかなければなりません。この機会に「クラウド×税理士」を検討されてみてはいかがでしょうか?
『FLAGSグループ』が“クラウド会計導入”をサポートします!
クラウド会計を導入したい!けど…「導入方法が全く分からない」、「上手く効率化できるか不安」、「今の税理士が対応してくれない」などなど。会計ソフトを導入し、使いこなすためにはさまざまなハードルがありますよね。マネーフォワードプラチナ公認メンバーの『FLAGSグループ』はクラウド会計導入支援実績400件超!クラウド会計未経験の方でも安心してお任せ頂けます。お気軽にお問い合わせください!
> 『FLAGSグループ』のクラウド会計導入(公式ページ)